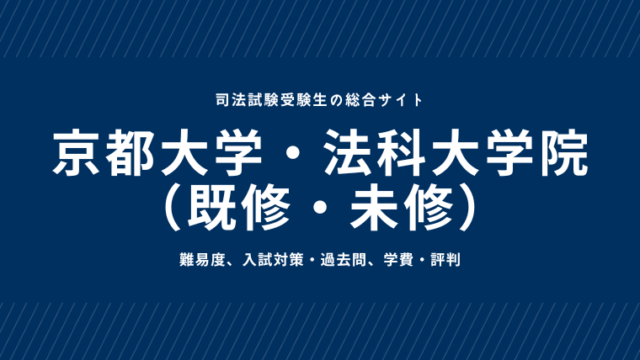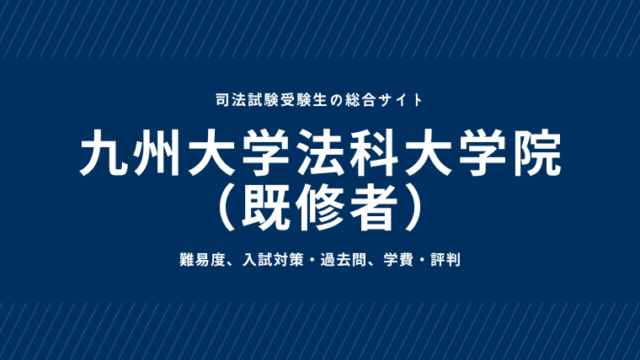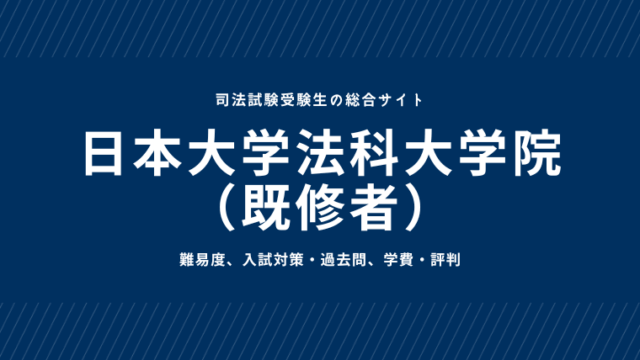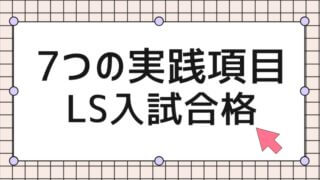慶應義塾大学大学院法務研究科は、2004年に開設した三田キャンパスに校舎がある法科大学院です。
慶應のロースクールは、司法試験の合格率が高く、法曹界でも高い評価を得ています。
国立の東京大学、京都大学、一橋大学とともに、
日本のトップロースクールとして高い評価を得ています。
事前に講座内容を確認しておきましょう!
\合格へのペースメーカー/

目次
慶應義塾大学・法科大学院の基本情報

| 名称 | 慶應義塾大学 大学院法務研究科 |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-8345 東京都港区三田2-15-45 |
法科大学院の司法試験合格実績(2023)
| 2023年度ランキング | 司法試験合格率 | 受験者数 | 最終合格数 | |||
| 順位 | ロースクール名称 | 全体 | 全体 | 修了者 | 在学中 | |
| 1位 | 京都大学法科大学院 | 68.4% | 275 | 188 | 94 | 94 |
| 2位 | 一橋大学法科大学院 | 67.2% | 180 | 121 | 61 | 60 |
| 3位 | 慶應大学法科大学院 | 60.0% | 310 | 186 | 95 | 91 |
| 4位 | 東京大学法科大学院 | 59.0% | 315 | 186 | 92 | 94 |
| 5位 | 神戸大学法科大学院 | 48.6% | 146 | 71 | 44 | 27 |
| 6位 | 名古屋大学法科大学院 | 47.2% | 89 | 42 | 22 | 20 |
| 7位 | 早稲田大学法科大学院 | 44.7% | 389 | 174 | 90 | 84 |
| 8位 | 大阪大学法科大学院 | 42.9% | 182 | 78 | 51 | 27 |
| 9位 | 中央大学法科大学院 | 39.3% | 229 | 90 | 43 | 47 |
| 10位 | 北海道大学法科大学院 | 37.8% | 74 | 28 | 13 | 15 |
| 11位 | 岡山大学法科大学院 | 36.4% | 33 | 12 | 5 | 7 |
| 12位 | 愛知大学法科大学院 | 33.3% | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 13位 | 成蹊大学法科大学院 | 33.3% | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 14位 | 筑波大学法科大学院 | 33.3% | 51 | 17 | 12 | 5 |
| 15位 | 同志社大学法科大学院 | 33.3% | 87 | 29 | 19 | 10 |
参照元:令和5年司法試験の結果について(2023年法務省)
慶應義塾大学法科大学院の司法試験合格率は、上位にあります。
ロースクール全体と比較すると、「未修コース」卒業生の合格率が高いことがわかります。
例年、慶應義塾大学法科大学院の司法試験合格率は高く、今後もトップロースクールであり続けると思います。
慶應義塾大学・法科大学院の学費
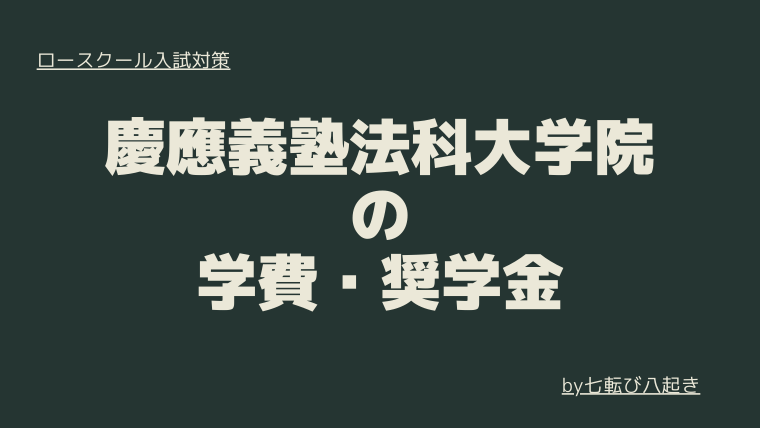
| 初年度学費 | 168万円強(2020年度) |
|---|---|
| 奨学金 | 奨学金制度あり |
▼アガルート「入試対策講座」の詳細▼
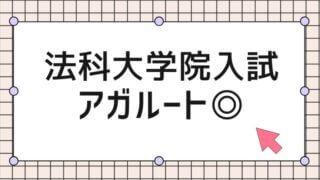
慶應義塾大学法科大学院に合格できる人(合否判定基準)
慶應義塾大学法科大学院では、以下の点数を総合評価して合否判定を実施しています。
- 法律科目試験の点数
- 志願者報告書(ステートメント)の内容
- 外国語試験のスコア
- 学部の成績
慶應大学法科大学院では、志願者報告書(ステートメント)の内容が重要視されています。記載内容次第で高い評価を受けるで、十分に検討した上で記載しましょう。
優れた外国語能力があれば慶應では評価されます。英語に限らず、得意な言語があればアピールポイントとして使えます。英語TOEICであれば900点以上が高評価の対象となります。
◉志願者が優れた法曹として社会で活躍するための十分な資質、潜在能力、意欲を備えているか否かを総合的に判断するための資料です。特に,大学等においてどのような問題意識に基づいて学習・研究を行ってきたか,さらに社会人としての経験を有する者についてはどのような経験をし,何を身につけ,それを通して法曹への意欲をどのように育んできたかを重視して判断するために用います。
◉多様なバックグラウンドを持った法曹の養成を促進するという見地から特色ある人材を特に評価します。
- 優れた外国語能力を有し、将来、グローバルに活躍する法曹を目
指している者- 理科系の学部・大学院を卒業・修了し(見込者も含む。)、将来、
その知識を活かして、学際的・先端的な法分野で活躍する法曹を目指している者- 成績優秀者として学部を早期卒業する見込みまたは「飛び級」の
見込みであって、当該学部において、特定の外国語や国際的な教養、
人文科学・社会科学の特定の分野について、インテンシブな教育を
受け,特筆すべき素養を有する者- 特定の分野で豊富な社会人経験を有し、将来、その経験を活かして、
特定の法律分野に秀でたスペシャリストとしての法曹を目指す者

慶應義塾大学・法科大学院の入試難易度
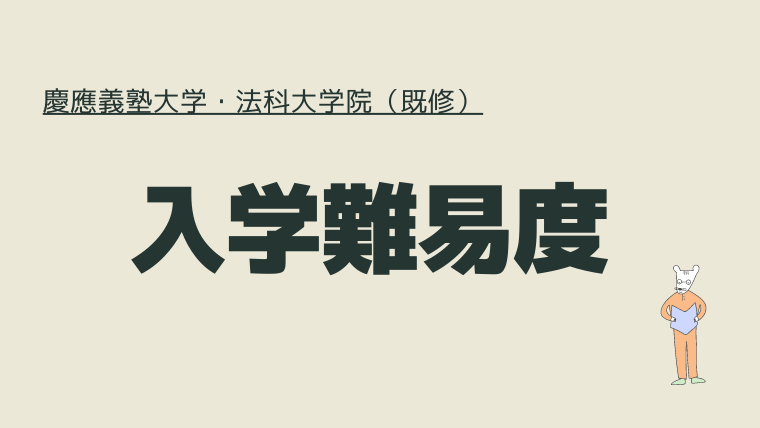
| 難易度 |
|---|
慶應義塾大学法科大学院は、私立の法科大学院の中では、司法試験の合格率がトップであるだけあって、難易度は高いです。
誰しもが、一度は入学することを検討する法科大学院です。
慶應大学出身であっても、落とされることは勿論あります。気を引き締めて受験対策することが重要です


慶應義塾大学・法科大学院⇒過去問の出題傾向(既修)
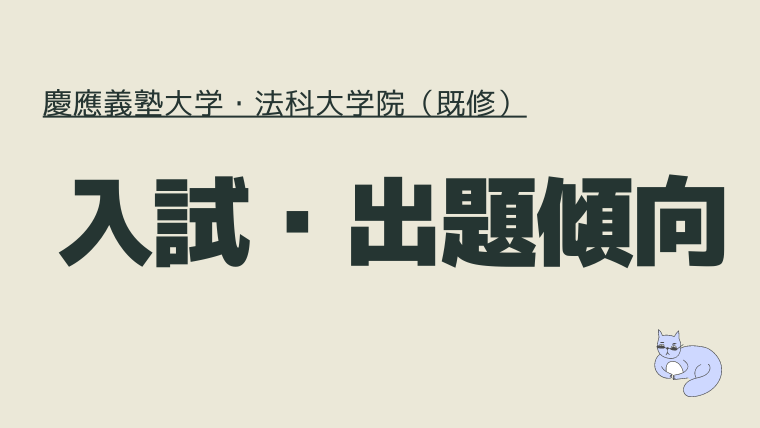
慶應義塾大学法科大学院を受験する際には、やはり過去問研究は必須です。
慶應ロースクールでは、受験者全員に対して、筆記試験(論述式試験:憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法)が実施されています。
特に慶應ローの民法試験は、応用力が試されます。
例えば、早稲田大学法科大学院は判例百選に載っている判例の論点がほぼそのまま問題になっていたり、中央大学法科大学院は原則的には、かなり基本的で平易な出題がされます。
それに比べると、慶應ローの民法問題は、基本ではありますが、応用ができないと正直きついと思います。
一方、憲法の問題はあまりに難しいということはなかったです。
刑法は問題形式に特徴があるので、それさえ注意すればそこまで難しいものではないですし、刑事訴訟法は書くべき論点がたくさんあるので時間との勝負になりますが、基本的な論点しか聞かれることはありません。
民事訴訟法は問題文をよく呼んで論点を抽出できれば大丈夫だと思います。商法も基本的な論点しか聞かれません。
慶應義塾大学法科大学院の受験難易度は高いと言いましたが、基本が大切です。しっかりと勉強することです。
試験本番では、時間配分に気をつけましょう。
慶應義塾大学・法科大学院⇒入試対策
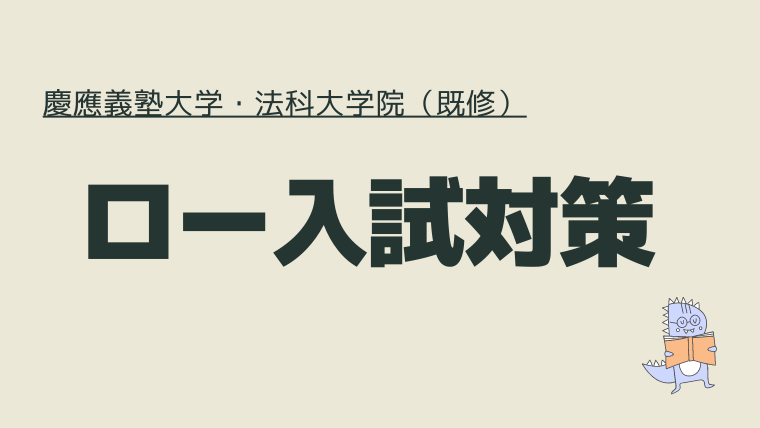
法科大学院入試の過去問を解くこと
慶應義塾大学法科大学院の入試対策として、まず言えることは、過去問をとにかく解きましょうということです。
法科大学院の受験の問題は、各大学院、各教科によって色々と形式が異なるので、自分が合格したいと思う法科大学院の出題形式に慣れておくことが非常に重要です。
私の場合、アガルートの法科大学院別の過去問分析講座を受講し、非常に役立ちました。
法科大学院の過去問分析講座は、アガルートが一歩抜きん出ていると思います。
\割引期間は低価格!/
各科目の入試対策
過去問を通じて、答案構成と自分が答案を書きあげるスピードを把握して、時間配分を自分の中できちんと決めておくことも大事です。
受験勉強にあたっては、何事も基本が大切ですので、基本的な論点は総復習しておきましょう。
私の場合、民法は旧えんしゅう本、刑法はスタンダード100、憲法は憲法事例演習、商法と民事訴訟法はLawPractice、刑事訴訟法は事例演習も使って、どれも一通り学習しました。
慶應の民法は、難しいですが、過去問を解いてよく出るところを分析するのがいいと思います。
憲法は、どの論点を聞かれてもいいように、学習しづらいとは思いますが、生存権や財産権、選挙権なども全てやはり論点は押さえてある程度の水準の答案は書けるように準備すべきです。
刑法は、大問の一つ目が、見て貰えばわかると思いますが、条文を指摘して理由を書くというものなので、基本判例の結論とその理由は百選で押さえておくのがいいとおもいます。
民事訴訟法、刑事訴訟法、商法はとにかく基本問題が出題されます。
ただ、本番の試験では、時間が足りなくなる可能性もあるので、自分の論証で長すぎるなと思うものは、要点だけ残して短くしたものを用意するのが良いと思います。

▼アガルート「入試対策講座」の詳細▼
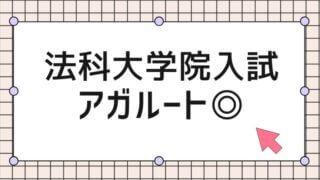
慶應義塾大学・法科大学院⇒内部生の口コミ・評判
法科大学院といえば、留年率が高いことが一般には知られています。
特に、早稲田大学法科大学院は留年率が高いことで有名です。この点、慶應義塾大学法科大学院は、留年する人はクラスで(前20-30名前後)で1人か2人くらいしかいません。
期末テストができなかったなと感じたとしても、白紙で提出するとか、採点不可能なくらいのよっぽどズレた論点を書かない限り、留年することはほとんどないということです。
慶應義塾大学法科大学院は、授業も司法試験に受かるための内容の授業を展開してくれています。
この点、一橋大学法科大学院や、東京大学法科大学院では、学術的なことや、自分の頭で考えることが鍛えられますが、授業は必ずしも司法試験合格だけを見据えているとは言えないそうです。
慶應義塾大学法科大学院の授業は、どの教科も予習復習が大変です。
しかし、予習段階でまず問題を解いて、授業ではその内容をソクラテスメソッドで教授が生徒を当てながら解説するような形で進むので、内容が頭に入ってきやすいです。
「司法試験ではこの論点は聞かれるor聞かれない、出そう」ということを教えてくれる教授もいます。
慶應義塾大学法科大学院の期末試験は難しいですし、きついですが、司法試験の本番では、そういうレベルの問題と闘っていくんだなということを実感できます。
慶應義塾大学ロー・スクールの受験生へ
慶應義塾大学法科大学院に合格することは大変です。落ちたらどうしよう、大学院受験で浪人したくないなという不安もたくさんあると思います。
私もそうでした。
でも、基本をとにかく押さえた勉強をして、過去問を解きまくっていけば大丈夫です。
試験当日は、自分ができなかったなと感じる問題は大体周りの人もできていませんので、特に気にすることなく、各教科ごと気持ちを切り替えて頑張って欲しいです。
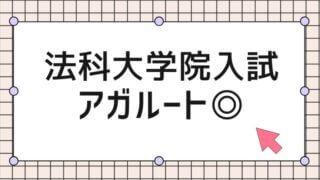
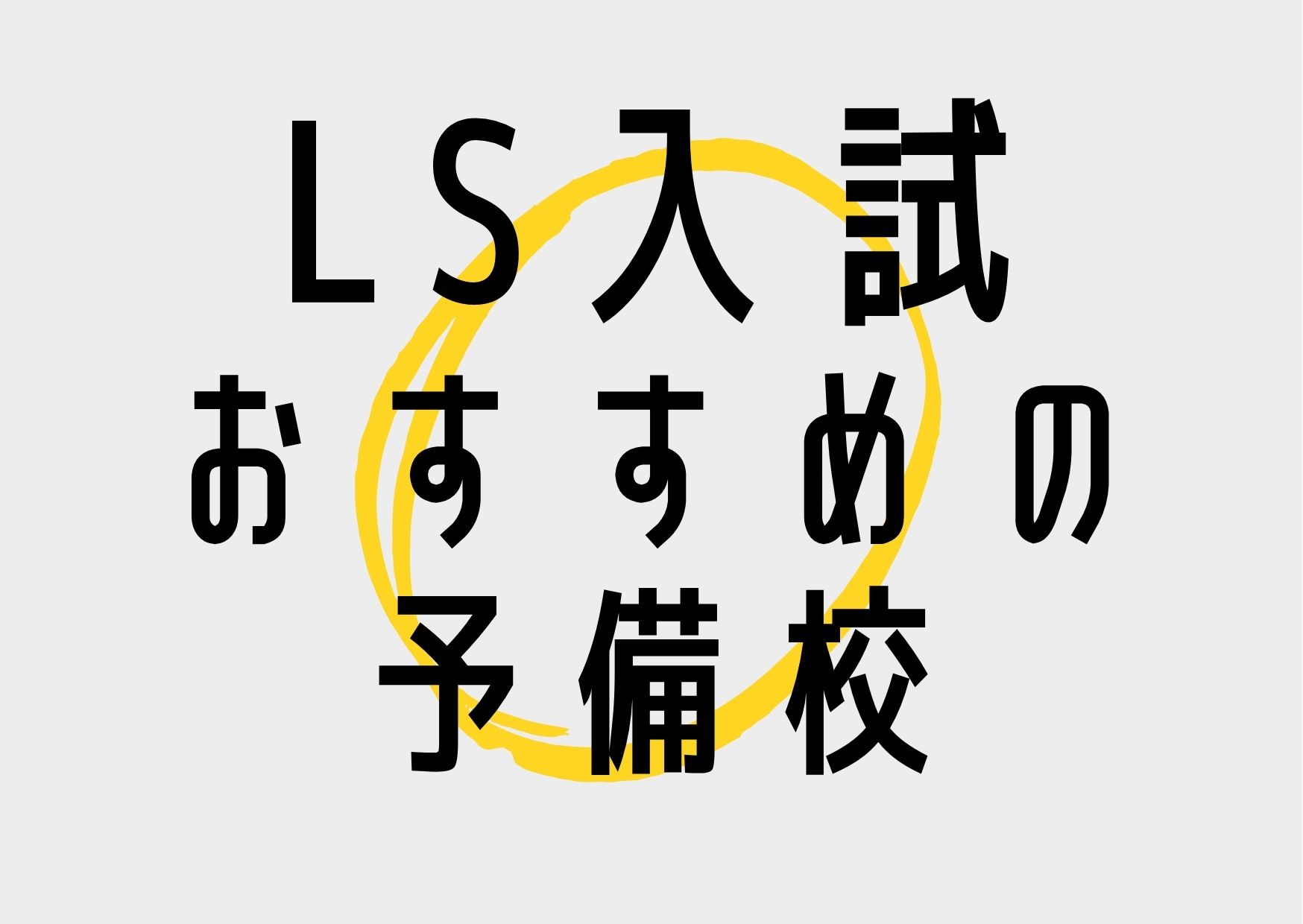 | 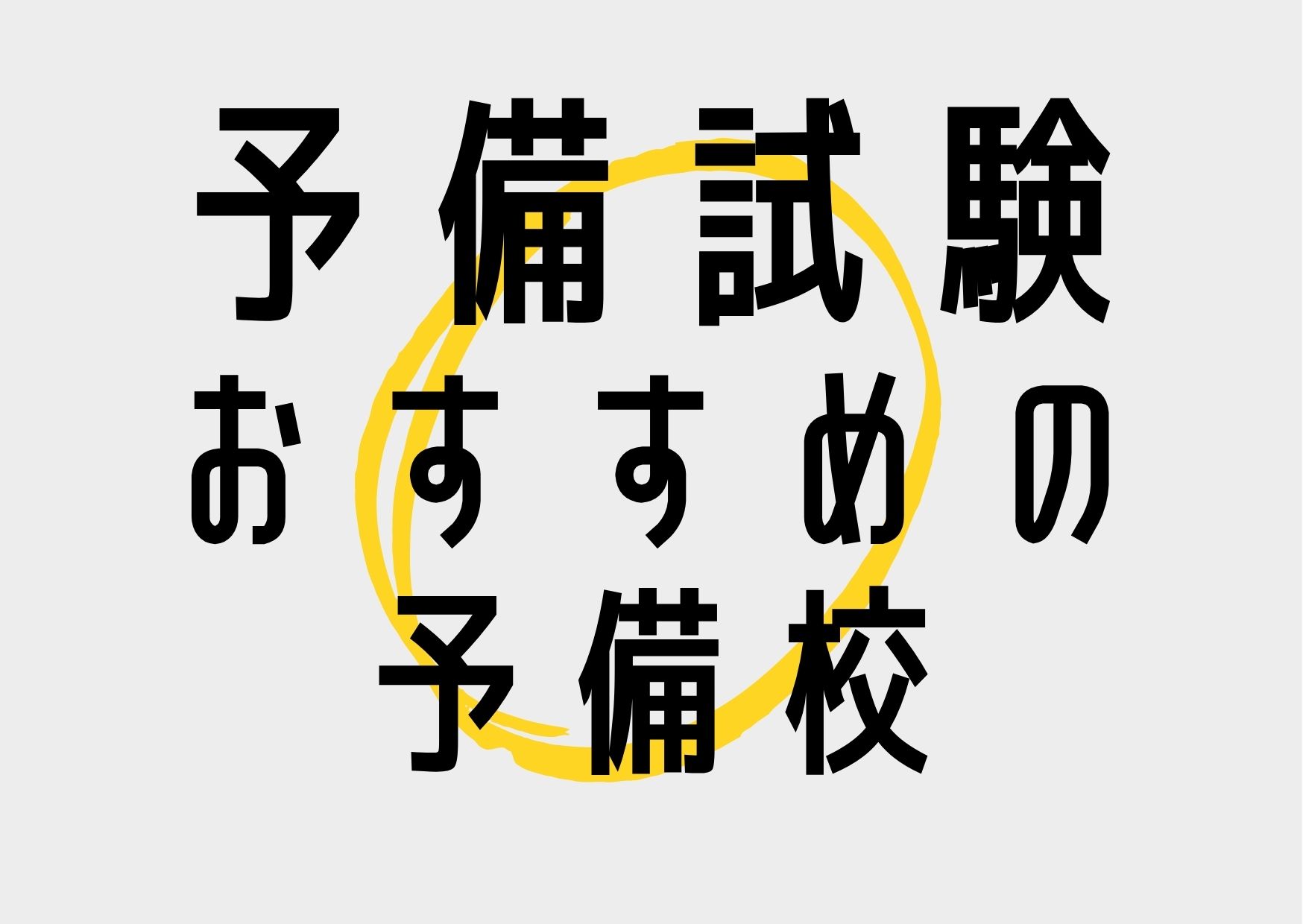 |
\合格者の評価が高い/
 アガルートには法科大学院の入試対策講座が充実しています。
アガルートには法科大学院の入試対策講座が充実しています。
公式HPを必ず確認しておきましょう。