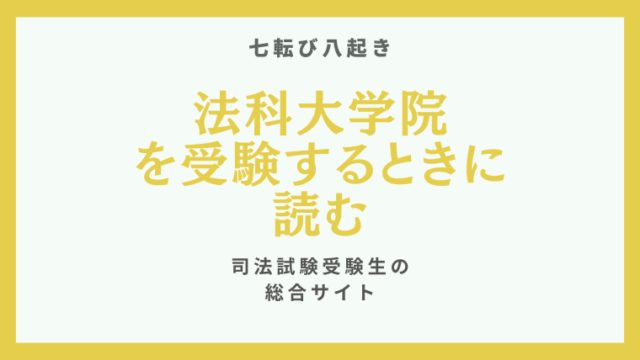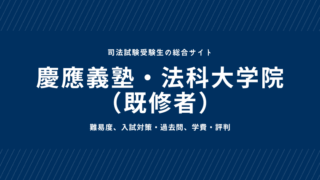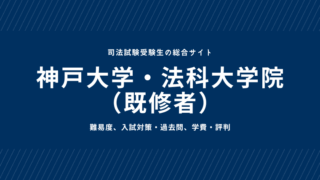法科大学院(既修)の入学試験に合格するために絶対実践すべき7つのこと
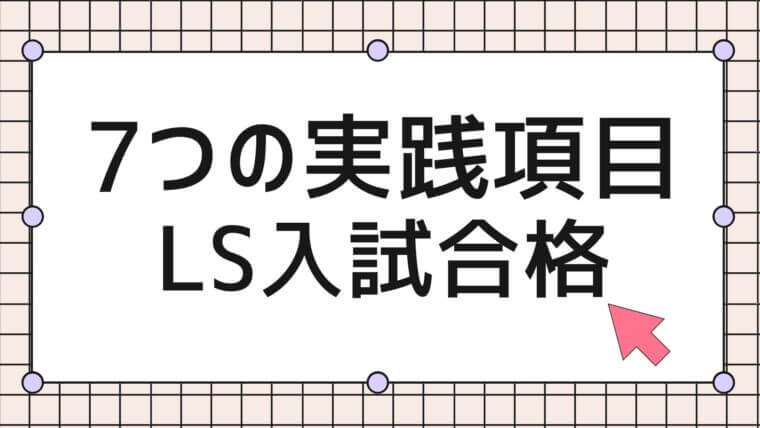
司法試験の受験資格を獲得するためには、法科大学院を修了していることが求められます。
法科大学院は、入学前に法律の勉強をしていない人を対象とした「未修コース」と、入学前に法律を勉強した人を対象とした「既修コース」があります。
今回は、法科大学院(既修コース)の入学試験に合格するために、絶対実践すべき7つのことをお話しします。
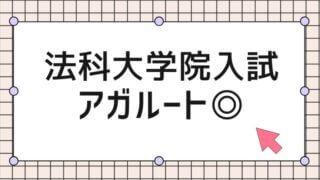
事前に講座内容を確認しておきましょう!
\合格へのペースメーカー/

目次
法科大学院入試(既修)に絶対合格⇒①受験計画を立てる
法科大学院への受験を考えたときに、まず、数ある法科大学院の中から受験する法科大学院を決めて、受験日までの計画を立てなければなりません。
出願書類を確認
受験を希望する法科大学院を絞り込み、募集要項から、試験日、出願期間、試験科目、出願書類を確認しましょう。
出願書類で重要なのは、志望理由書(ステートメント)です。
外国語試験のスコアが有利になることも
TOEIC(R)テストやTOEFL(R)といった語学試験のスコアの任意提出もあります。一部の法科大学院(一橋大学法科大学院など)では、TOEIC・TOEFLのスコアが良ければ、試験合格に有利に働く可能性があります。
大学時代の成績も関係
各法科大学院では、論述試験と志望理由書・大学時代の成績・外国語試験のスコアとの配点比率は異なります。
例えば、大学時代の成績が良い場合、論述試験の配点比率が低い法科大学院を受験する方が有利ですよね。募集要項を確認するなどして、自分にとって有利な法科大学院の受験を検討してください。
私立・国公立の法科大学院の試験日
また、私立の法科大学院の試験日は7月〜9月、国公立の法科大学院の試験日は10月〜11月に多く実施されます。
国公立の法科大学院を第一志望とする方は、私立の法科大学院入試を一つの腕試しとして受験することもできます。
法科大学院入試(既修)に絶対合格⇒②入試科目を確認
法科大学院入試(既修)の場合、司法試験と同様、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の7科目が出題される法科大学院があれば、
行政法、商法は出題されない法科大学院もあります。各法科大学院で試験科目が異なります。
また、法科大学院によっては、科目の試験範囲が限定されていることもあります。
折角勉強したとしても、学習範囲が、試験の範囲外であれば勿体ないですよね。効率よく勉強するためにも、受験する法科大学院の試験科目とその範囲は必ず確認しましょう。
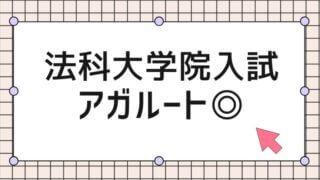
法科大学院入試(既修)に絶対合格⇒③志望理由書(ステートメント)
多くの法科大学院では志望理由書の提出が求められます。
志望理由書に求められる内容は各法科大学院で様々ですが、どの法科大学院でも、自分のなりたい法曹のイメージを具体的に記述することが求められます。
法曹が身近にいない大学生の段階で、法曹の業務をイメージすることは難しいと思います。しかし、法曹を目指す先輩からお話を聞いたり、法律事務所のホームページを覗いたり、新聞などで最新の情報を追ったりするなどして、抽象的な記述で終わらないようにしましょう。
受験生の中には「志望理由書で差はつかない」として、適当に書いてもよいと考える受験生も一部いるようです。しかし、本当に差がつかないなら、法科大学院側はわざわざ受験生に志望理由書を課さないでしょう。
志望理由書を書くことで、自分の法曹になりたい思いに改めて気づくこともできますし、できるだけ真剣に作成することです。できれば周りにいる先輩や友人、両親など他人に見てもらって感想を聞くなどして、推敲してください。

法科大学院入試(既修)に絶対合格⇒④論文式試験対策
法科大学院入試も、司法試験も「論文試験」の答案を書くことが重要です。
講義を聞くことも重要ですが、
論文答案を書かなくては、到底合格することができません。
なるべく早い段階から、定期的に論文答案を書く学習習慣を構築しましょう。書きながら覚えると言うスタンスが重要です。
大事なことなので繰り返しますが、
「論文答案を書かないと、一生合格することはできません」
わかりやすい予備校を利用しつつ、実際に手を動かして論文答案を書く練習をしてください。
問題文を読むときは、
- 先に設問を読み、問われているポイントを把握する
- ポイントを頭に入れながら問題文を読む
- 答案構成をする
- 答案を書く
上記のようなステップで処理してください。
法科大学院の入試時間は短いです。にも関わらず各文字数(答案の枚数)はたくさんです。
合格するためには、問題演習は不可欠です。
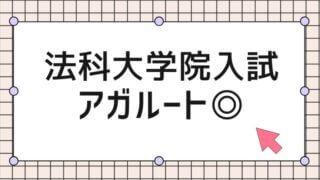
法科大学院入試(既修)に絶対合格⇒⑤問題集・演習書
折角知識を身につけても、それをどのように活かすか分からなければ、知識がないのと同じです。法科大学院入試では、知識がどのように聞かれているのか、問題集や演習書を解くことで知りましょう。
問題集を解く際も、知識をインプットする場合と同様、分からない問題に固執せず、特に一周目はできるだけ早くまわしていきましょう。問題を解きながら、出てきた条文や論点を確認し、知識の定着も同時に図っていきましょう。
独学の場合、問題集や演習書は、自分にとって解説の分かりやすいものを各科目1冊ずつ選びましょう。
しかし、様々な問題集や演習書が出版されていることから、初学者が選ぶのは難しいかもしれません。また、解説を読んでも理解できないこともあるでしょう。このような場合、予備校の問題演習講座を受講することがお勧めです。
予備校の講座では、その問題の解答、解説だけでなく、問題を読んだときの頭の使い方を教えてくれます。他の問題への応用の仕方や、問題のポイントも丁寧に解説してくれるからです。
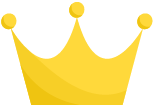 法科大学院別で対策するなら「アガルート」
法科大学院別で対策するなら「アガルート」| 合格者オススメ度 | |
|---|---|
| 値段 | 安価(オンライン予備校) |
| 特徴 | 法科大学院別の対策講座が充実 |
法科大学院入試(既修)に絶対合格⇒⑥法科大学院入試の過去問
過去問を解く前に、過去問の出題形式を確認することが必要です。
多くの法科大学院では事例問題での出題が多いですが、一行問題を出題する法科大学院もあります。出題形式によって、答案の書き方や勉強方法も変わるので、必ず確認しましょう。
そして、過去問を解く場合は、答案構成だけで終了せず、時間配分を気にしながら答案を実際に書くことが重要です。実際に答案を書くことは骨の折れる作業ですが、ぜひ逃げずに頑張ってください。
法科大学院入試の過去問を解く場合には、各法科大学院の出題の趣旨を確認することです。自学で適切な解答筋を見つけるのは受験生にとって難しい場合もあるでしょう。
法科大学院入試の過去問の解説集などは、一部の予備校講座以外では、市場に出回っていません。
法科大学院の入試問題を解説している予備校の講座を受講すれば、適切な解答筋だけでなく、当該法科大学院の問題の傾向とそれに沿った勉強法を教えてくれるため、正しく、効率的な勉強をすることができます。
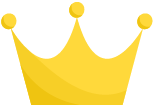 法科大学院別で対策するなら「アガルート」
法科大学院別で対策するなら「アガルート」| 合格者オススメ度 | |
|---|---|
| 値段 | 安価(オンライン予備校) |
| 特徴 | 法科大学院別の対策講座が充実 |

法科大学院入試(既修)に絶対合格⇒⑦反復学習を
過去問を解きながら、理解の曖昧な分野が判明した場合は、該当箇所について基本書を読むなどして知識を入れたり、問題集の問題を解いたりするなどしてください。
何度も反復してください。何度も反復することで知識が定着します。
法科大学院(既修)入学試験の合格に向けて
ロースクールに合格することは憧れの法曹三者になるための第一歩です。
ロースクール合格に向けての勉強は、ロースクールでの勉強、ひいては司法試験合格のために必要なものです。
大変ですが、一生懸命頑張りましょう。
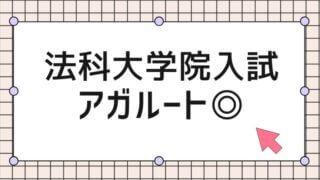
\合格者の評価が高い/
 アガルートには法科大学院の入試対策講座が充実しています。
アガルートには法科大学院の入試対策講座が充実しています。
公式HPを必ず確認しておきましょう。