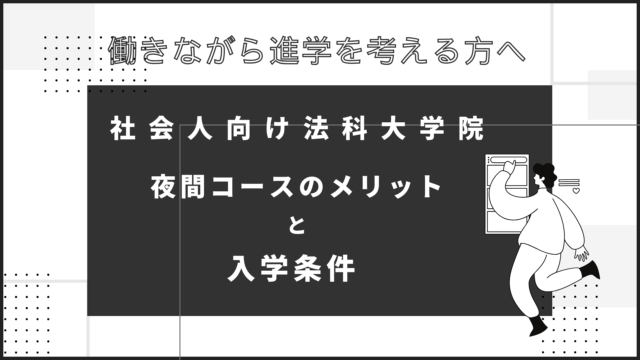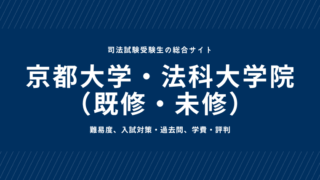合格経験を踏まえて、合格に向けた小論文対策についてお話しします。
目次
法科大学院の小論文試験の特徴
小論文試験の特徴
まず、法科大学院の小論文試験の特徴として、問題文の長さがあげられます。特に事例問題やある文章に対する意見を述べさせるような試験だと、問題文だけで数ページから十数ページになることも珍しくはありません。
そうするといくら試験時間が長くても、問題文の読み込みに時間がかかってしまい、解答を作成する時間は短くなりがちです。
そこで、試験が開始したらまず問題の分量や問いに対する解答がどのくらいの長さになりそうかをざっと確認し、時間配分を決めることが大切です。
そして試験前には必ず、実際の試験時間と同じ時間で過去問を解いてみましょう。何度か解くうちに時間の感覚が分かってきますので、余裕を持って解答を作成できるようになります。
問題を読み解く力
また法科大学院の小論文試験では、文章力や法律家に不可欠な論理的思考のほか、社会で起こる問題に対する多角的な視点や、相手が何を問い掛けているのかを読み解く力も要求されます。
そこで普段から論理的思考の練習や時事問題に関心を持ってニュースを見ていると、試験のときにどのような題材が出ても焦らずに論理的な解答を書くことが出来るのではないかと思います。
法科大学院の小論文試験に合格する書き方・秘訣・対策
そこで、法科大学院の小論文試験に合格するための書き方を解説したいと思います。
基本的には、
- 小論文の枠組みを意識すること
- 自分の意見を理由とともに述べること
- 矛盾のない論理的な文章を書くことです。
もっとも、小論文自体はだいたいの枠組みを押さえて書けば、構成的には問題がないかと思いますので、そこまで難しくはないでしょう。
法科大学院の小論文試験⇒書く時の注意点(流れ・枠組み)
ここでは、大まかな枠組みについての解説と、小論文を書くときに注意すべきポイントについて触れたいと思います。
まず、小論文の流れとしては、一般的にこのような流れで書くことが多いかと思います。
① 問題提起
② 問に対する答えや自分の意見を端的に
③ ②のような考えを持った理由を説明
④ 反対意見に触れる
⑤ 結論
① 問題提起
まず①に関しては、問題文に問題提起があればそれを、なければ自分で簡単に考えて書く必要があります。はじめに問題提起をすることで何について論じるかが読み手にも分かりやすくなりますし、全体の流れを作るのに重要な部分です。
② 問に対する答えや自分の意見を端的に
次に②に関しては、①問題提起のあとすぐに問に対する答えや自分の意見を述べることで、その論文の方向性が分かりやすくなります。
さらに先に問いに対する答えを述べることで、万が一試験時間が足りなくなり中途半端なところで解答をやめなくてはいけなくなったとしても、最低限の答えは書いていると評価はしてもらえるかと思います。
小論文にありがちなのが、長い解答のなかで自分の意見や具体例などを書いているうちに、問いに答えないままになってしまうことがあげられます。これは問題の問いに答えていないとして評価が低くなる恐れもありますし、注意すべきポイントです。
③ ②のような考えを持った理由を説明
さらに③では、②で端的に述べた問いに対する答えに詳細な理由を書く必要があります。どんな意見も理由がないと説得力がないので、複数の理由や具体例をあげられるといいかと思います。
④ 反対意見に触れる
そして④では、自分の意見とは異なる意見や反対意見に触れます。そのような意見に対して、自分の意見の方が正当性があるという説明や具体例があることでより説得力が増します。
⑤ 結論
⑤では、もう一度②で述べた問いに対する答えや自分の意見を書いて解答をまとめます。
②から④で自分の意見について色々と論じたうえで答えることで、最終的な結論がはっきりとします。
〜まとめ〜
以上が小論文の大まかな枠組みになりますが、もちろんこの枠組みでは対応が難しい問題が出ることもあると思います。
そのような場合でも、自分の意見とその理由を書くこと、問いに対して答えることをの2点が意識できれば一定の評価を得られるのではないでしょうか。
今まで小論文の試験を受けた経験がなかったり、試験に向け不安を感じる方は法律系予備校での小論文講座や、本屋さんで売っているテキストを使って対策をすると安心できると思います。
ロースクール受験生にオススメの法科大学院
司法試験合格を目指すうえで、オススメの法科大学院をいくつか紹介したいとおもいます。
法科大学院では「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」が導入され、合格実績や国際化・女性の推進など学校ごとの取り組みを基に、文部科学省によって類型が分けられており、国公立・私立の法科大学院の類型が発表されています。
そこで今回はその中から現時点で最高評価のSをとった国公立・私立の法科大学院それぞれひとつづつ紹介します。
東京大学法科大学院
一校目は東京大学法科大学院(正式名称・東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻専門職学位課程)です。いわずもがな、日本で最高峰の国立大学のひとつです。
早稲田大学法科大学院
そして二校目は早稲田大学法科大学院(正式名称・早稲田大学大学院法務研究科)です。
私立の大学で最高評価のSを取得したのは慶應大学法科大学院と早稲田大学法科大学院の二校のみです。
両校とも大学院の所在地は都内で、規模も大きいことから勉強する環境や仲間には恵まれるのではないでしょうか。
また私立の早稲田法科大学院では学校側のサポートも手厚く、未修入学者にはチューターが付き、学習面だけでなく生活面での相談もできる環境が整っています。
さらに早稲田法科大学院では通常の夏入試のほか、冬入試という制度もありますので、チャンスは2倍になります。
未修者で受験するときに、オススメの予備校・通信講座・本
法科大学院への入学を「未修枠」で検討する場合には、
「入試対策はどうしたらいいの?」
と迷いガチです。
未修受験の対策を独自に実施することは、合格という観点からは非合理的です。
必ず信頼のある予備校から情報を集めるようにしてください。
現在、ロースクール入試(未修枠)の受験対策として、一定の評価を得ている予備校の講座は、
『LEC』
で開講しているものとなります。
オススメの予備校は「LEC」
まず、未修受験の方が検討することが多いのは、予備校講座としては大手のLEC講座が挙げられます。
LECでは法科大学院入試に向けた小論文対策講座や、ステートメント(志望理由書)の書き方講座が用意されています。
LECのなかでも法科大学院入試直前講座は短期で、人気のある講座となっています。

ロースクール受験生(未修コース)に向けて
法科大学院入学は司法試験合格に向けての第一歩になります!そのため、みなさんの目標に向けた努力が実ることを心から願っています。
\合格者の評価が高い/
 アガルートには法科大学院の入試対策講座が充実しています。
アガルートには法科大学院の入試対策講座が充実しています。
公式HPを必ず確認しておきましょう。