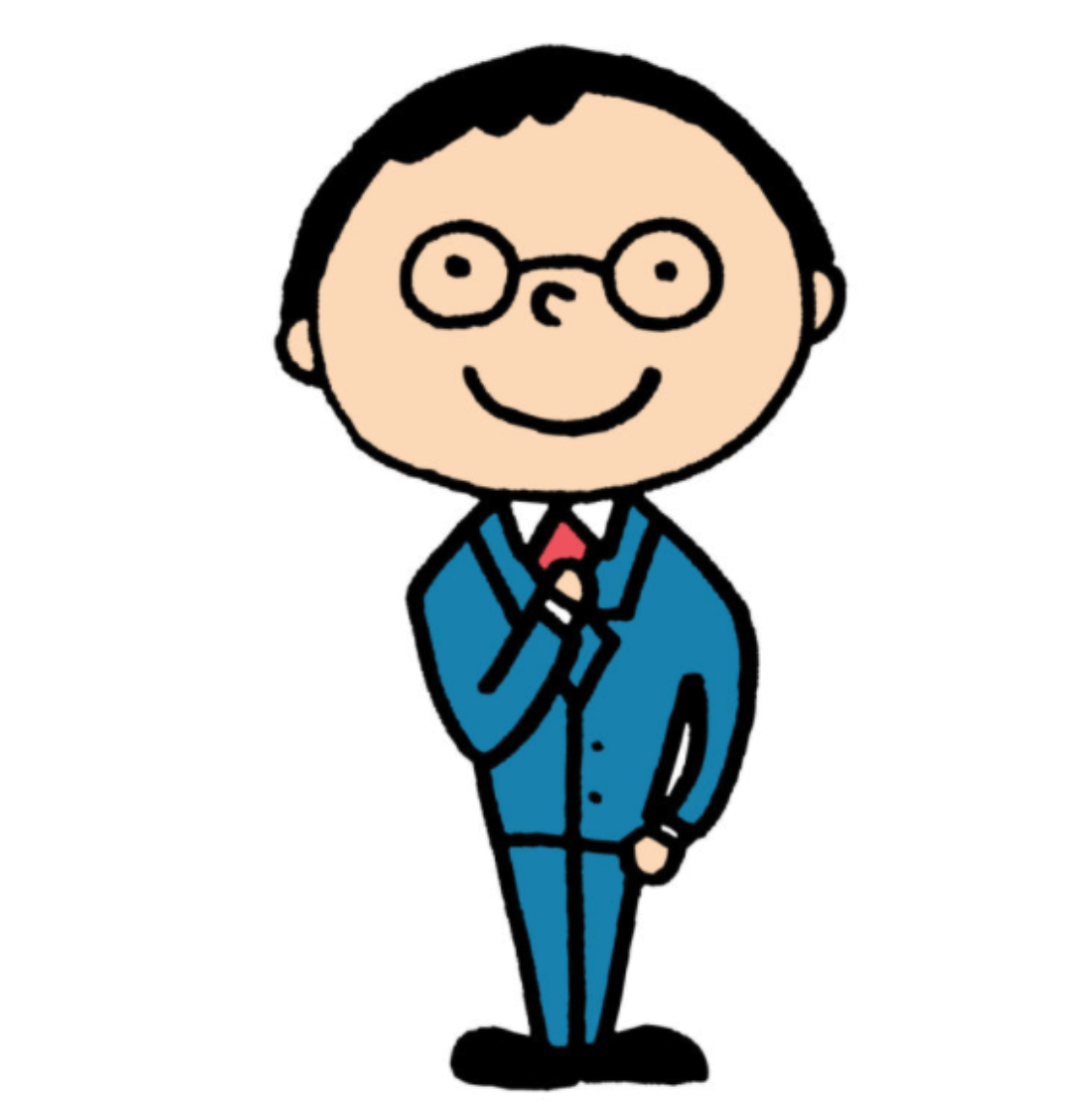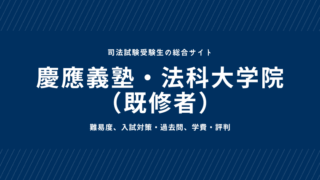合格者に聞く⇒法務部・コンプライアンス部の人が「予備試験を絶対受験」すべき理由(ステップアップ)
会社で、法務・コンプライアンスの仕事をしている人に向けて書いています。
法務系の仕事をしている人は、学生時代に法律の勉強経験がある人が多いと思います。
そうでなくても、仕事では「法律実務の最前線」で仕事をしているのであり、法律を学ぶ上でこの上なく良い環境に身を置いているわけです。
今の時代、自分のスキルを高めながら働くことが必要となりますが、今後、業務をさらにステップアップさせるときには、やはり法律系の資格試験の勉強をすることになると思います。
どうせ資格を取るならば「予備試験の合格」を目指していると良いと思うのです。
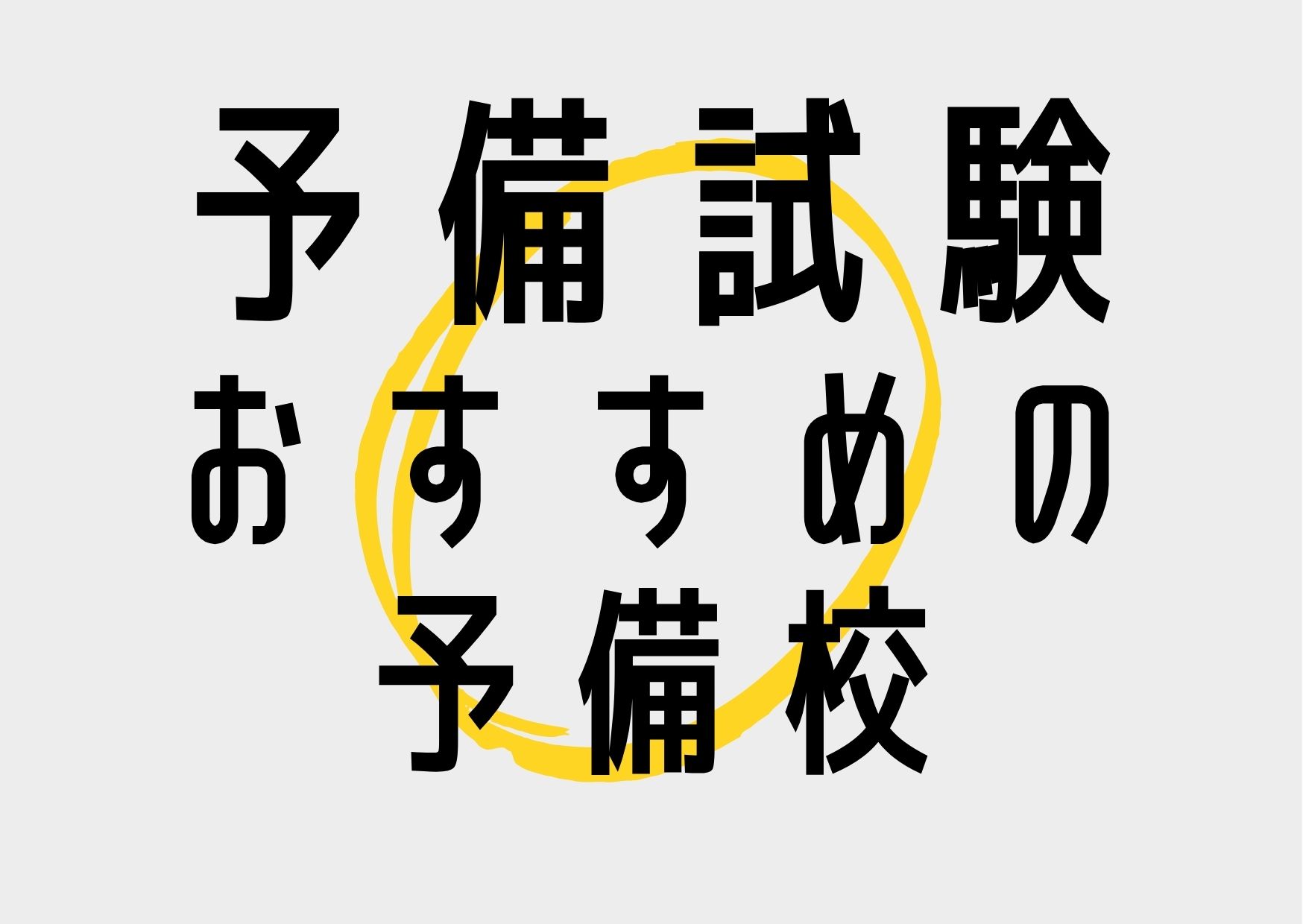 | 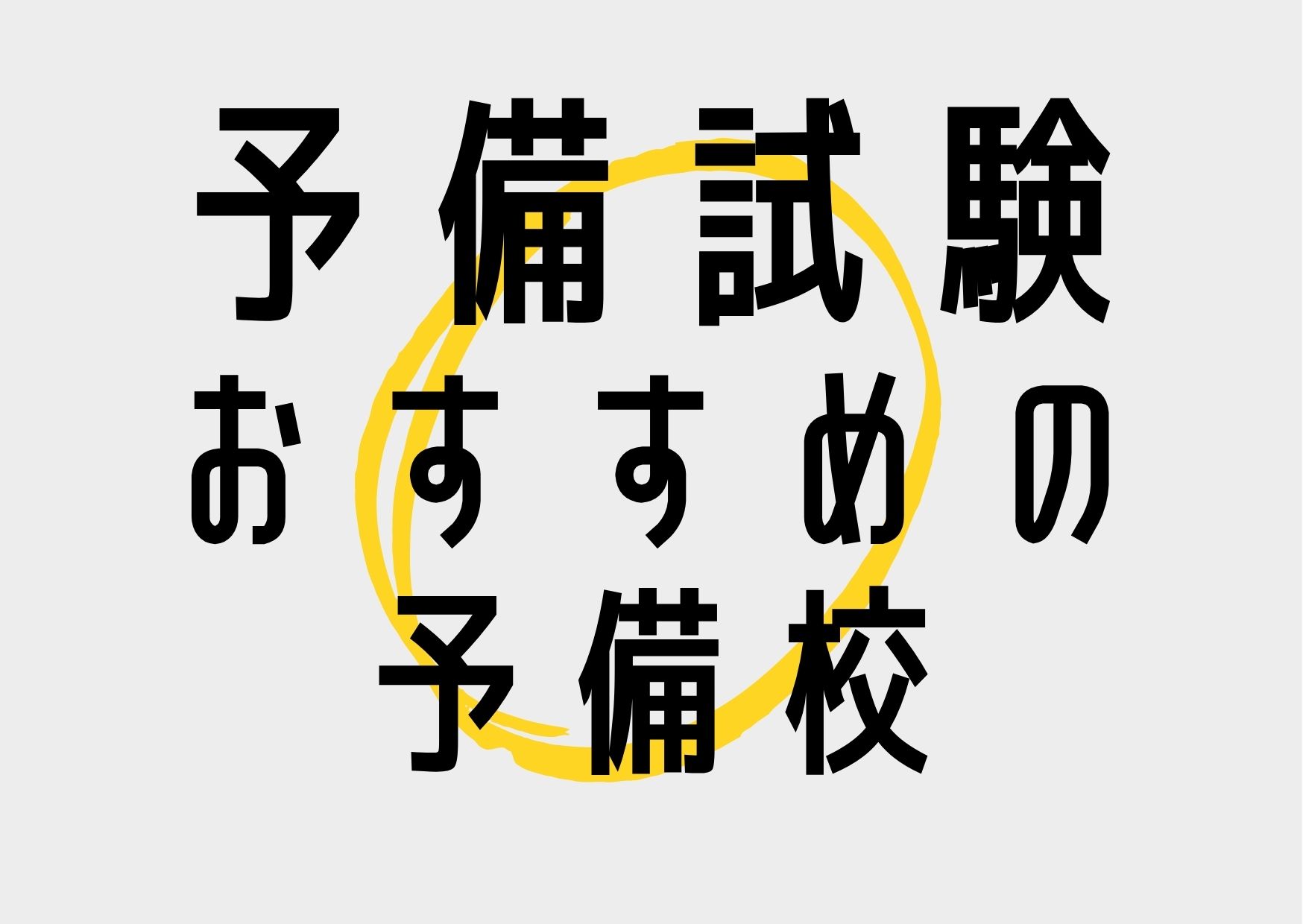 |
目次
理由①ステップアップの手段としては予備試験が最適
予備試験で学ぶ内容は、法律の基本事項でありますから、仕事に生かすことができますし、普段の勉強にも生かすことができるはず。
それに、予備試験に合格しておくと社内外において、あなたの評価が一気に上がります。
理由②これからの時代、資格武装しておかないと不安定
昨今では、法律系の仕事量に比べて、弁護士資格を有する人の割合が増えてきていると言われています。弁護士の数が割と多くなり、弁護士が仕事を探し回る傾向にもあります。
弁護士数の多さにも比例して、企業内弁護士として働く人の数も増えてきており、資格を保有していない人は、社内弁護士に仕事を奪われやすい状況になっています。
それに、これからの時代はIT化が進み、契約審査の自動化など、法律系の仕事が減少することも予想されているのです。仕事の奪い合いになる可能性も秘めています。
司法試験に合格するまでは必須腕はないけれど、その前段階である予備試験には合格しておくことで、他の人と大きく差別化を図ることができるのです。
企業としては弁護士資格を持つ人を雇いたいわけではありません。弁護士だと独立できるので簡単に辞めてしまうし、弁護士は性格的に問題がある人が多いので扱い難いのです。
それに対して、予備試験合格者や法科大学院卒業生は、外部弁護士を使いこなし、企業内の法務系の仕事を取りまとめる役割として重宝される傾向にあります。
理由③予備試験に合格することは簡単に
また、今の時代、予備試験に合格することは、昔の司法試験に比べると、かなり容易になっています。
司法試験・予備試験の試験科目
まず、予備試験の試験科目を確認しておきましょう。
| 短答試験 | 論文試験 | 口述試験 |
| ■法律基本科目 (憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)■一般教養科目 (人文科学、社会科学、自然科学、英語) | ■法律基本科目 (憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)■法律実務基礎科目 (民事訴訟実務、刑事訴訟実務及び法曹倫理) | ■法律実務基礎科目 (民事、刑事) |
| ■一般教養科目 ※ (人文科学、社会科学、自然科学) |
※2022年(令和4年)から、論文試験の一般教養科目は廃止されます。代わりに「選択科目」が導入される予定です(司法試験法第5条第3項)。
科目数が多いので、多くの方は、
「こんなに沢山勉強しなければいけないのか」
「超大変ではないか」
と考えてしまうことでしょう。しかし、そんなことはありません。
合格に必要となる科目は少なく、合格レベルは低いので、学習範囲と量はグッと狭まります。
予備試験短答式試験の合格ラインは6割
皆さんに確認して欲しいことは、予備試験の場合、短答試験に合格には、6割ほどの正答率(全270点中165〜170点)で足りるということです。
予備試験の短答式試験は、個別の「科目別の合格最低ライン」基準は設定されていないので、
一般教養科目の得点が0点でも、全科目の合計で合格点を超えれば短答式試験には合格できます。
法律科目の配点は「全270点中210点」を占めるので、法律基本科目で8割取れれば十分に合格基準点に到達します
一般教養科目は適当にマークして正解すればラッキーくらいの感覚で大丈夫でしょう。
予備試験論文式試験の合格ラインは5割以下
論文式試験の得点割合は、以下の通りです。
- 法律基本科目 350点
- 法律実務基礎科目 100点
- 一般教養科目 50点
このうち、最近では合格点は240点ほどと考えておいて良いでしょう。
法律実務基礎科目は、対策が難しいと思います。
でもそれは他の受験生においても同じことであり、多くの受験生は得意科目にすることが困難でしょう。つまり、受験生間では差はつき難く、ここで合否は分かれることはないと思います。
予備試験に合格するという観点では、あくまで勝負は法律基本科目なのです。
理由④予備試験は受験生のレベルが高くない
それに、予備試験においては、現在のところはまだ受験生の学力レベルは高くありません。多くの方が初学者レベルであり、初学者でありながら合格していきます。
現代の予備試験の場合、受験生の主流は、大学生か法科大学院生です。
大学生は、法科大学院と併願しており、予備試験に不合格となれば、法科大学院に進学するか受験を一度中断して就職する方がほとんどでしょう。
また、法科大学院生の場合にも、卒業すれば司法試験を受験できる為、予備試験を毎年受ける方はほぼいません。
結局、毎年受験生が入れ替わっており、法律初学者が受験生の大半であるという実態があります。
法務・コンプライアンス部の人は予備試験を受験
現在、お仕事で法律系の仕事をしている人は、いずれかの段階では是非「予備試験」を受験してみるべきだと思います。
どうせ受験するならば早い方が良いと思います。
予備試験は、自分にはまだ早いと考えている人は「ビジネス実務法務検定」や「宅建試験」「行政書士」といった法律系の資格を取得すると良いでしょう。
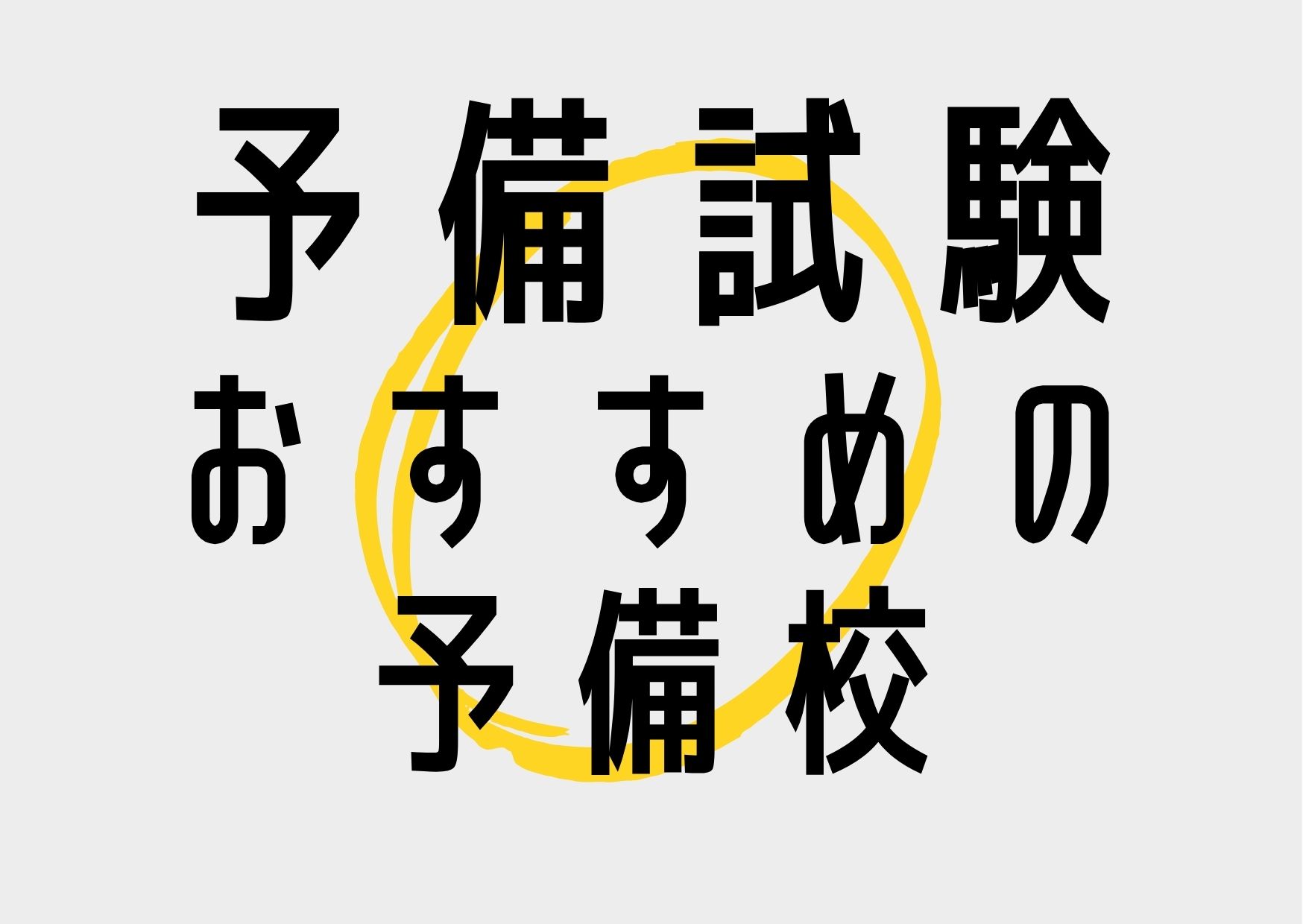 | 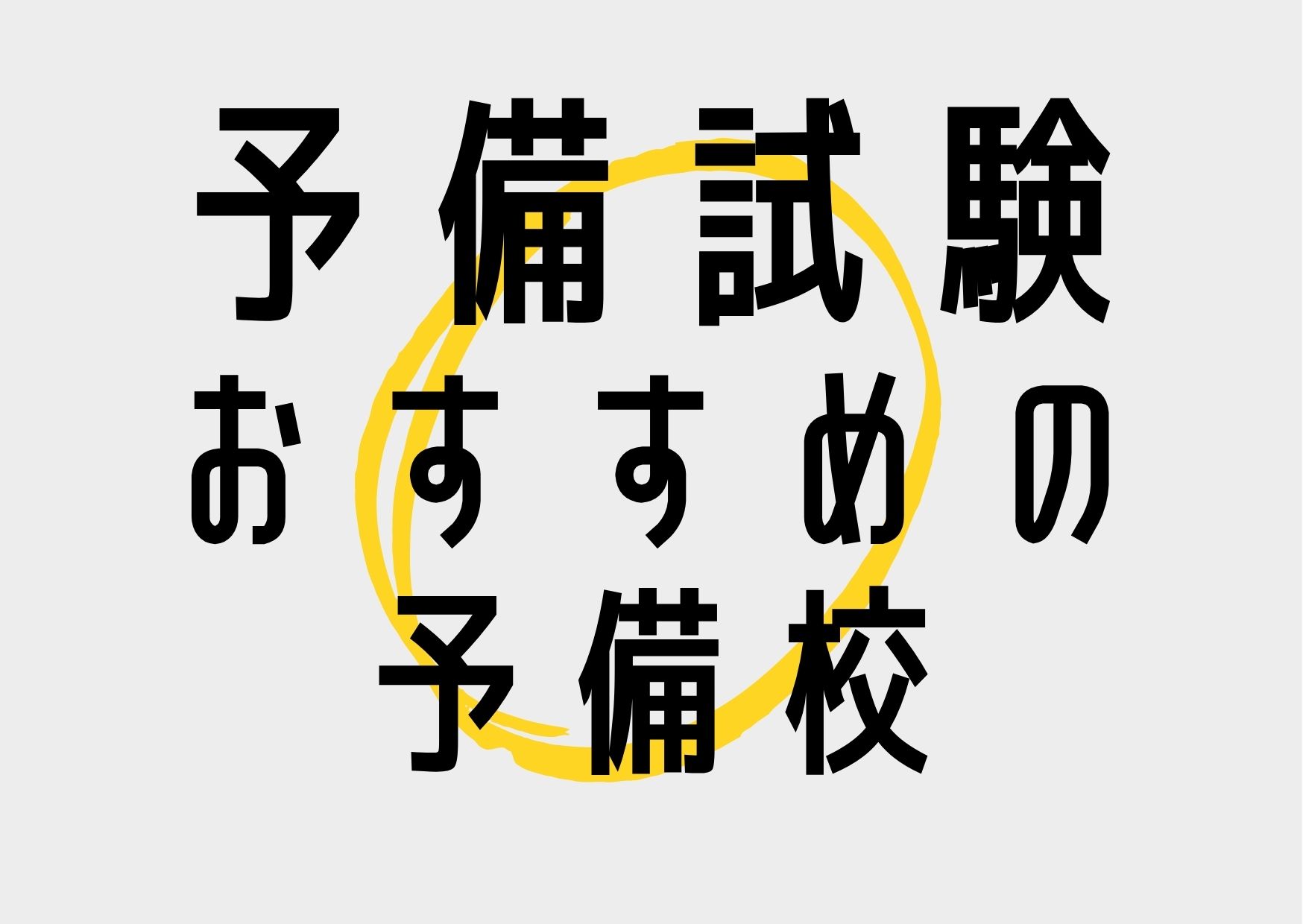 |
\ 合格者の評判◎/
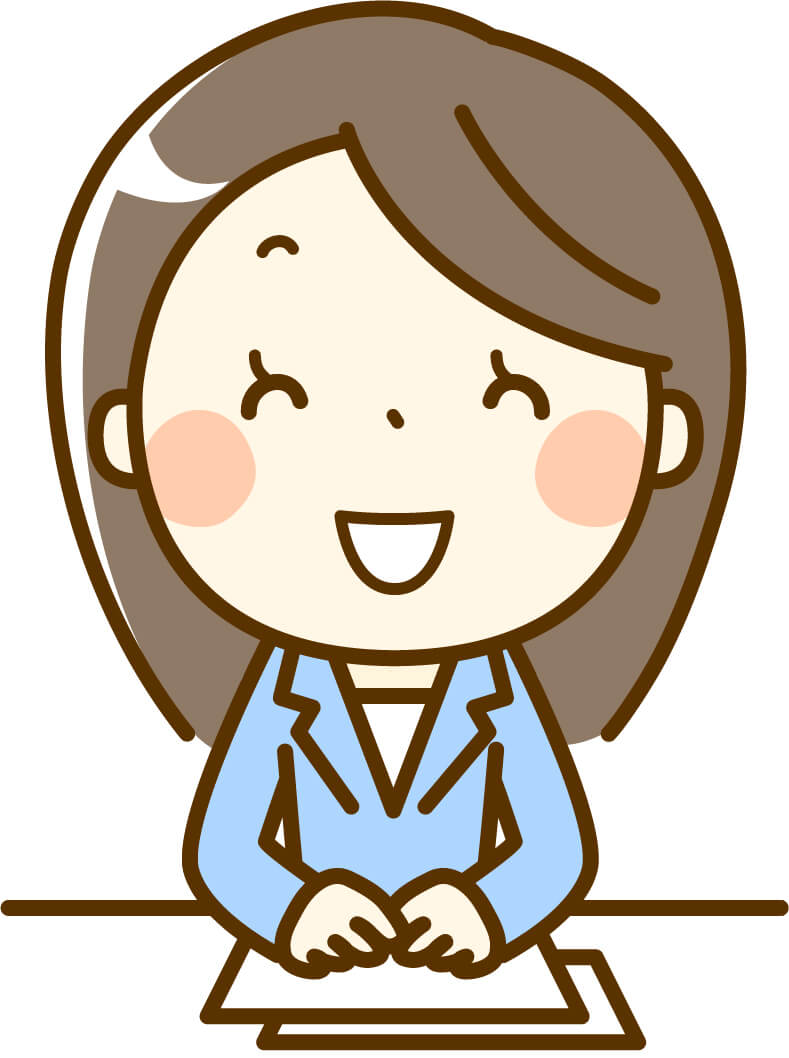 資格スクエアは、合格者にとっても評判が良いオンライン予備校です。
資格スクエアは、合格者にとっても評判が良いオンライン予備校です。
公式HPで必ず確認しておきましょう。