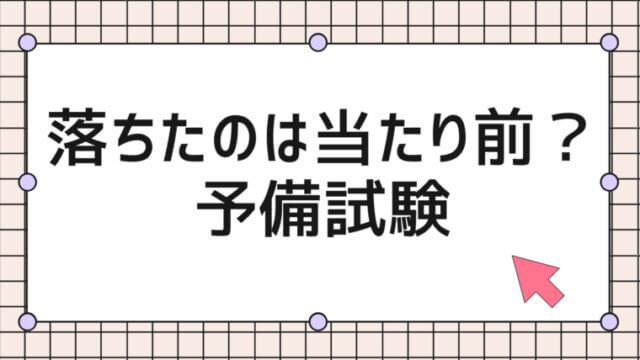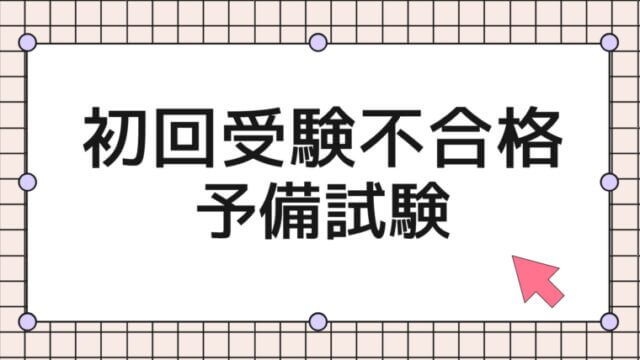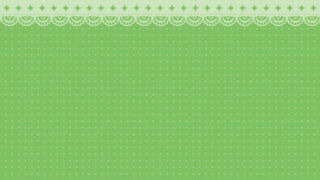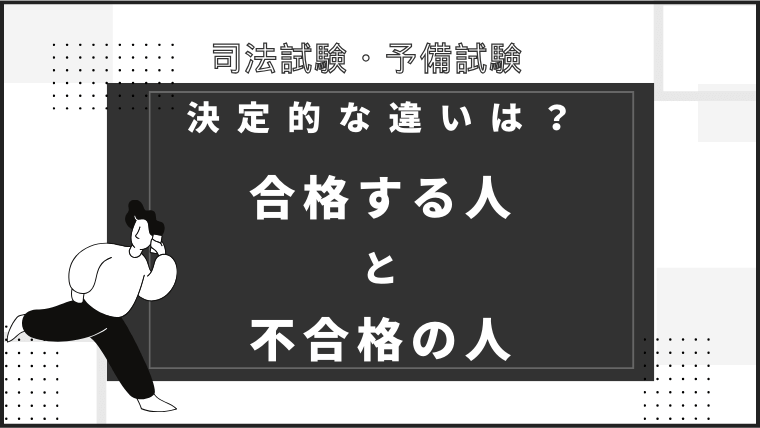
予備試験と司法試験を何度も挑戦する中で、「試験に合格する人」と「不合格になる」人の違いがわかりました。
合格する人には「共通した特徴」があり、
不合格になるにも、「共通した特徴」があります。
合格者と不合格者には明確な特徴(違い)があるのです。
自分が「合格者」の性質を持つのか、「不合格者」の性質を持つのか。
自覚して改善することが重要です。
試行錯誤しながら、自分自身を変革していくことで合格は確実に見えてきます。
本気で合格を目指すとき、必ず確認してください!
\合格へのペースメーカー/

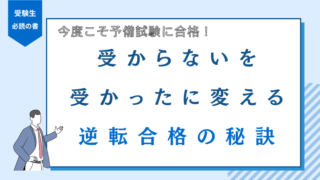
目次
受かる人と落ちる人の違い① 暗記は不要
予備試験・司法試験に不合格になる人は、暗記勉強に一生懸命になります。
しかし、
予備試験・司法試験(論文)は、本来的に暗記が不要な試験です。
基本的に「暗記が不要」と言うことを理解できているか?
この点に合格者と不合格者の差異があります。ではなぜ、司法試験に暗記がいらないのでしょうか。
法律の文章(論文答案)は、以下の①〜④で構成されています、論文答案を書くとき同じです。
- 自分の主張
- 法律的な根拠
- 法律要件検討
- あてはめ
上記のうち①は自分の主張を書けば良いですから、そもそも暗記不要です。
②法律的な根拠も、六法の条文を探せば良いだけです。
③法律要件の検討についても、趣旨からその要件の詳細を合理的に考えれば良いので暗記不要ですし、
④あてはめも、問題文から事実を引っ張ってくるだけです。
予備試験・司法試験に落ちてしまう人は、特に③法的要件と④事実のあてはめについて、思慮深く考えてない傾向にあります。これでは合格することは不可能です。
受かる人と落ちる人の違い② 完璧主義かどうか
テキストの読み方→熟読・詳細まで完璧主義
合格者と不合格者の違いのうち、特徴の一つとして「テキストの読み方」が挙げられます。
司法試験・予備試験に受からない人は、勉強熱心となるあまりに、テキストや基本書を読むときに、最初から最後まで読み込もうとする典型的な特徴があります。
「何ヶ月もかけて基本書を熟読する」
しかし、一から十までテキストを熟読して、完全理解しようとする勉強方法は危険です。司法試験・予備試験の不合格推定が働きます。
なぜなら、
司法試験・予備試験の(短期)合格者は基本書やテキストを熟読するというインプット型の勉強方法は行いません。熟読するよりも論文答案を書いたり、過去問を解く勉強スタイルを採用しているので熟読する時間はないのです。
基本書やテキストには合格には必要がない無駄なことが多く書かれています。
例えば基本書やテキストに書かれている重要部分は、その本の2割だけだと言われています。基本書等を読むときにはその本に書かれている重要事項(2割)は何なのか?ということを考えて、エッセンスのみを読み取ることこそが必要なのです。
司法試験・予備試験に受かる人は、その法律の基本事項を簡単にまとめた入門を2〜3冊読んで、法律の骨格を抑えてしまいます。インプット学習においては要点だけを押さえることに意識を向けているという特徴があります。
基本を抑えた後は過去問を解いて、論文問題の答案を書く中で疑問に感じた点のみを「試験対策講座」などを辞書がわりにして調べています。必要部分のエッセンスだけを押さえるようにしています。
疑問点についてだけを参考書となる教材を辞書代わりに調べるのです。テキストは読み込みものではありません。
それに基本書・テキストを読む際にも自分の頭で考えるようにしており、インプット時間は最小限にしてアウトプットの時間を確保するようにしています。
司法試験・予備試験に不合格となるか、合格できるかは、テキストの読み方ひとつで推し量ることができます。特に伊藤塾を受講している人は熟読派が多いので注意が必要です。
試験範囲:捨てる分野と拾う分野を見極め
司法試験・予備試験に受からない人は、真面目な受験生が多いという特徴があります。
不合格となる人は向上心が高くて、「上位合格」を狙ったり、「満点」「完全理解」という高い目標を持って勉強しているという特徴があります。
しかし、完璧主義だと、司法試験・予備試験においては不合格推定が働くので注意が必要です。
真面目さや向上心がアダとなって、試験に落ちやすい体質に陥っている人を多く見かけます。
司法試験と予備試験は、出題範囲が広すぎるし、また問われている内容も奥深いモノがあるので、
完全理解することはそもそも不可能だからです。
司法試験・予備試験に受かる人は、合格ラインを越えればいいと割り切り、必要最小限の容量がいい勉強を心がけている特徴があります。
試験の合否は、受験生間において相対的に決まります。司法試験・予備試験に受かるには試験科目範囲を完全マスターする必要がありません。
法律の骨格だけを理解した上で、過去問を理解・記憶してさえいれば、司法試験・予備試験に合格することができます。
勉強対象を、ガッツリ絞り切ること。そして繰り返して勉強すれば、実は予備試験と司法試験は簡単に合格できます。
受かる人と落ちる人の違い③ 勉強方法
小まめに期限を設定→期限遵守
司法試験・予備試験に受かる人は、勉強するときには、学習期限を設定する特徴があります。期限の締切を設けると集中力が増し、また学習能力が向上するからです。
学習期限を設定することで、
「合格するためにはどのような勉強をしなくてはいけないか」
「この法律の重要ポイントは何か」
「どの試験範囲を重点学習しなければいけないのか」
ということを必然と考えながら勉強できますし、また実践的に使える理解力と記憶力が身につきます。
司法試験・予備試験に受からない人は、学習期限を設定しないか、または期限設定しても期限を遵守することができないという特徴があります。
期限遵守を徹底できないと、期限までに勉強が出来なかったことによるモチベーションの低下があります。
司法試験・予備試験の本試験当日までに期限を何度もこまめに設定しましょう。何度も何度も期限を設定することで能力向上の機会が増えるため学習能力が向上します。
設定する締切日が一度だけだと、試験に対応できる能力をあげることは難しいと思います。
繰り返し、反復継続学習を
司法試験・予備試験に受かる人は、
本試験当日まで、試験範囲を何度も何度も繰り返して学習するという特徴があります。試験範囲を何度も繰り返す中で、理解と記憶の質も深まります。
とりわけ、
要領が良い合格者は、反復継続学習を何度も繰り返す中で、同じ試験範囲の勉強時間を徐々に短く設定していきます。1回目は2週間、2回目は1週間、3回目は3日間というように学習スパン設定します。
学習締切日(試験当日)に向けて、自分で自分を追い込む学習をする合格者が多いと感じます。
受かる人と落ちる人の違い④ 逆算スケジュール
司法試験・予備試験に受からない人は、頑張り屋さんの方が多いという特徴があります。
傍目から見ると「ものすごく勉強」しているように見えますが計画性に欠けるように見えます。
目の前の勉強については頑張るのだけど、試験合格へのロードマップ全体の思考計画に欠ける傾向があるのです。
試験に落ちてしまう「頑張り屋さん」は、
自分に与えられた環境や、今までの勉強経験を踏まえて、自分に出来る勉強を精一杯に学習します。
マイベストを尽くして勉強しているのだから、何も悪いところはないように思えますが、
しかし、自分ができることを一生懸命に勉強するだけでは決して合格することは出来ないでしょう。
司法試験・予備試験に受かる人は、合格に必要最小限のことに的を絞り、試験当日までの学習計画を整然と立てる特徴があります。
司法試験・予備試験に合格したければ、合格年次を見据えて勉強しましょう。
目の前にぶら下がっている予備校授業の復習や、論文答練だけに目を向けた勉強をするのではなく、試験当日から逆算して、具体的な勉強計画を立てることが重要です。
「自分はいつ合格するのか?」
予備試験・司法試験い合格する日にちを決めてから、合格から逆算して学習スケジュールを立てましょう。
具体的に
「何をどこまで学習するのか」
ということを逆算でスケジュールしてから勉強しなければなりません。
本気で合格を目指すとき、必ず確認してください!
\合格へのペースメーカー/

受かる人と落ちる人の違い⑤ 試験対策を始める時期
司法試験・予備試験に落ちやすい人は、本格的な試験対策を始める時期がとても遅いという特徴があります。
真面目であるがあまり、目の前の予備試験の講義について予習復習に励みすぎる傾向があります。それ自体は悪いことではないのですが、
大手予備校では、基本講座の学習期間を1年半とか2年間の合格コースを設定しているので注意が必要です。
例えば、伊藤塾のように講義時間や予習復習の量や、教材のボリュームが多い予備校を選んでしまうと、受講生は1年半とか2年間で基礎講義の全て学び終えるだけで時間と体力が一杯一杯になってしまいます。
2年経ったところで、ようやく本試験に向けた受験勉強に本腰を入れる傾向があります。
本格的に勉強を始める時期が、1年半後・2年後からになるのです。モチベーションも若干下がっています。それにこの勉強方法は予備試験・司法試験の(短期)合格者の勉強方法ではありません。
一方、司法試験・予備試験に受かる人は、ある意味不真面目と言いますか、要領よく勉強するという特徴があります。
特に短期合格する人は、大手予備校のインプット講義学習に時間をかけすぎることがありません。
予備試験・司法試験の合格者から勉強方法を教えてもらって、論文答案の作成というアウトプット中心の学習を最初から心がけているのです。学習システムとして「資格スクエア」などのオンライン受講を受講することが多いです。
隙間時間も利用しながら、インプット学習を短期間で終わらせてしまいます。その法律の大まかな骨格を理解できたら、早々に本腰を入れて受験勉強を開始するのです。
大手予備校の基礎講座から受講して、1年半とか2年間の講座コースを受講している方は注意しましょう。伊藤塾のような大手予備校は、講義時間と教材のボリュームが非常に多いので、講座の予習と復習に明け暮れてあっという間に2年間が過ぎてしまいます。
2年間が過ぎてからようやく、本試験に向けた勉強をすることになってしまいます。
受かる人と落ちる人の違い⑥ 過去問の学習時期
過去問の学習法においても、不合格者と合格者には違いがあります。
司法試験・予備試験に受からない人は、過去問題を重宝し、大事に取り扱う傾向があります。過去問を大切にするがあまりに過去問を解く時期が遅いという特徴があります。受験勉強の終盤、試験直前期になって初めて過去問を見ることがあるのです。
結果として、過去問に対する理解は浅く、過去問の読み込みも出来ないままに本試験を迎えることになるのです。
これに対して、司法試験・予備試験に受かる人は、最初から過去問を使って勉強するという特徴があります。法律は過去問で勉強します。
司法試験・予備試験の合格者の多くは、基礎講義を聞き基本をマスターできたら、直ぐに過去問題を解き始めます。
過去問を解いたら、直ぐに解答と解説を読んで、自分の理解との本試験とのギャップを確かめます。これを何度も繰り返します。
何度も何度も過去問を解きます。
予備試験と司法試験の合格者は、
- 過去問題で「本試験の出題のされ方」を確認し、
- 過去問でその法律の「出題範囲」を理解し、
- 過去問を理解して過去問知識を覚えてしまう
合格者は、過去問で勉強しています。
過去問にも、
二度と出ないようなCランクテーマの問題が、2〜3割程度入っています。Cランクテーマの問題は飛ばして、頻出のAランクの典型的パターン問題が確実に解けるようにすること。出題パターンと解法パターンをアタマに入れておくことが重要となります。
受かる人と落ちる人の違い⑦ アウトプットとインプット
司法試験(予備試験)に不合格となる人は、インプット学習を重視し過ぎるという特徴があります。
不合格者は、皆「論文試験の答案」を書く練習をしていません。
特に、伊藤塾などの大手・通学生予備校の講座を受講すると、「インプット学習」がメインとなってしまい、講義を聞く受け身の勉強に偏重してしまいがちです。
しかし、司法試験・予備試験に受かる人は、「アウトプット学習」を重視する特徴があります。合格者の真似をしなくては合格は近づいてこないことに注意してください。アウトプットは基本の学習を終えたら直ぐに始めましょう。
アウトプット(論文の答案作成、短答の問題を解く)することで、理解力と記憶力も上昇していきます。アウトプットの数を増やすことこそが、合否を分ける決め手となります。
受かる人と落ちる人の違い⑧ スキマ時間の利用
司法試験・予備試験に受かる人は、一日中、試験合格に向けた努力をする特徴があります。
試験合格に向けて計画した学習スケジュールに従って、いま自分がやるべき勉強に、毎日、全力で意識を集中させています。
勉強する場所は、図書館や予備校、自習室、自宅の机に限りません。
移動中の歩いている時でもさえも、絶えず頭の中で勉強しているし、トイレやお風呂でも、寝ている時にも勉強のことで頭がいっぱいなのです。
電車の中などのスキマ時間を利用して、オンライン上で問題を解くというアウトプットを繰り返しています。
その反面、
司法試験・予備試験に受からない人は、移動時間などの隙間時間を有効活用しきれていない特徴があります。
受かる人と落ちる人の違い⑨ 学習範囲・選択と集中
予備試験・司法試験に合格したいのであれば、学習量(学習範囲)にも気をつけなくてはなりません。
勉強しない範囲を意識的に作りましょう
司法試験・予備試験に受からない人は、試験の出題範囲外についても勉強していますし、必要以上に掘り下げて深く細かいところまで勉強する特徴があります。
受験生の中には、勉強量や学習範囲は多いほど良いという勘違いをしている人がいますが、それは断じて間違いです。
闇雲に勉強しても予備試験・司法試験に合格することはできません。
司法試験・予備試験に受かる人は、合格するために必要な最低限のラインを見極めながら学習範囲を決めているし、どこまで深く理解すべきかについても判別するという特徴があります。
受験勉強は、出題範囲を見極め、出題形式に沿って、学んだ内容をまとめていく作業でもあります。
出題範囲の全てを完全マスターすることは不可能だということを理解して、合格するために必要となる学習範囲を絞るようにしましょう。絞った学習範囲だけをマスターするように心がけましょう。
特に直前期は「やらないこと」を明確にして「やるべきこと」のみを繰り返し勉強しましょう。
取捨選択が非常に重要になってきます。
予備校の「直前講義」を受講したくなるのもわかります。誘惑も増えてきますが、大切なのは自己管理です。使えない武器を持つことは有害ですから、
不要なこと、必要なことを決めて、徹底しましょう。
受かる人と落ちる人の違い⑩ 睡眠時間
司法試験・予備試験に受からない人は、受験勉強に熱心となるあまり、精神的に焦り、睡眠時間を削ってまで勉強する特徴があります。
本気で試験に合格したいのであれば、本試験当日までの学習計画に従い、やるべきことをやったら直ぐに寝るようにしましょう。
司法試験・予備試験に受かる人は、十分な睡眠時間を確保する特徴があります。
朝型でも夜型でも構いませんが、1日の睡眠時間は7〜8時間は確保するように気をつけてください。
そのためにも、何を・どこまで・いつまでにやったら良いのか?という、合格から逆算した学習スケジュールを立てましょう。
本気で合格を目指すとき、必ず確認してください!
\合格へのペースメーカー/

受かる人と落ちる人の違い11 合格者の真似をする
司法試験と予備試験に合格する人は、素直に合格者の話を聞くという特徴があります。最新の合格者からはなしを聞く機会を作って、合格者の真似をするように心がけています。
一方、
司法試験・予備試験に受からない人は、自分の勉強スタイルに固執する特徴があります。
確かに、自分の意見や考えを持つことも重要ですが、予備試験と司法試験の場合、合格者の話を数多く聞くことが重要です。
多くの合格者が実践していることや、注意していること、そして合格者の思考方法について学ばなくてはなりません。合格者と比べて、自分が異なっていることがあるかないか、絶えず意識しておきましょう。
予備試験・司法試験に合格するためには、合格者の真似をすることが一番なのです。
不合格者の特徴はどのように直す?
本試験まで残されている時間は僅かですから、なるべく早く自己変革を遂げる必要があります。
予備試験と司法試験の合格者の特徴を兼ね備えるべく努力をすることで、自ずと合格推定が働くようになるからです。
独学で自分1人だけで頑張ることは難しいので、
予備校など第三者の力を借りて、自分の中にある「不合格者の特徴」を排除する努力が必要です。

\合格者の評判◎ /
 アガルートにはあらゆる講座があります。初学者にも学習経験者にも評判が良いオンライン予備校です。
アガルートにはあらゆる講座があります。初学者にも学習経験者にも評判が良いオンライン予備校です。
公式HPを確認しておきましょう。