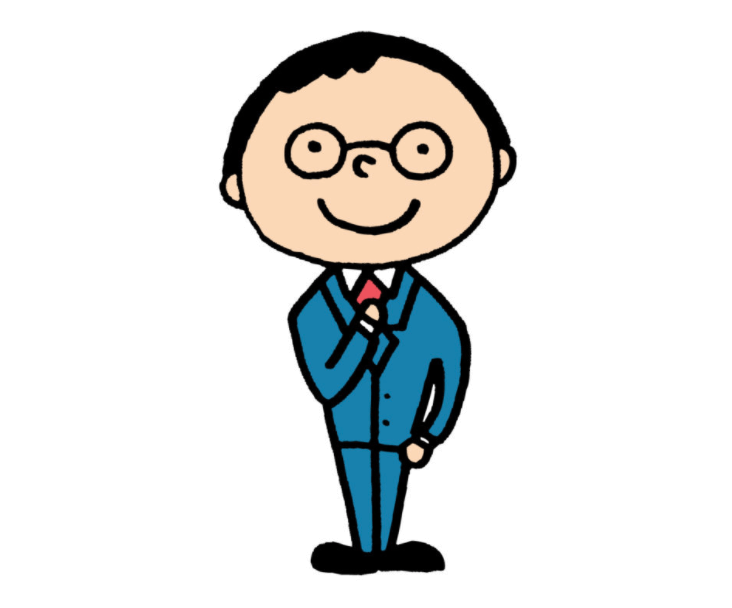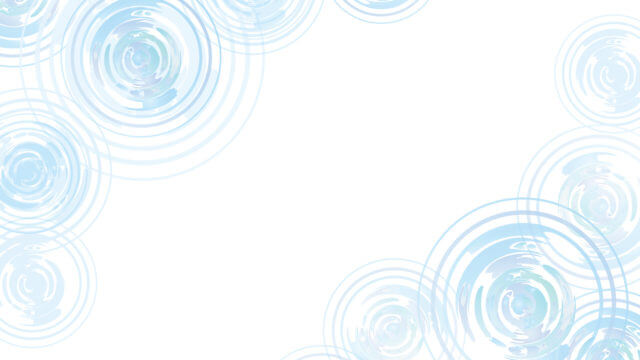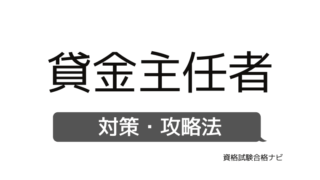宅建試験の試験概要
| 受験資格 | 制限なし(年齢・学歴等に関係なく誰でも受験可能) |
|---|---|
| 申込書配布 | 例年7月上旬〜 |
| 申込受付期間 | 例年7月上旬〜7月中旬(郵送の場合7月下旬頃迄) |
| 試験実施日 | 例年10月の第3日曜日 午後1時〜3時(2時間) |
| 出題形式 | 四択(マークシート方式) |
宅建試験の出題範囲
| 出題範囲 | ①宅建業法・②権利関係・③法令上の制限・④税その他 の4科目に分類 |
|---|
宅建試験の出題範囲は相当広いです。
特に民法を勉強したことがない人は、ある程度の学習期間が必要となります。
しかし、不動産のことや法律のことについて、はじめて勉強する初学者の方でも、1年間ほどで合格する方が多いので安心してください。
正しい勉強方法で学べば、必ず合格することができます。
宅建試験の科目、問題数
| 問題総数 | 50問 |
|---|---|
| ①宅建業法 | 20問 |
| ②権利関係 | 14問 |
| ③法令上の制限 | 8問 |
| ④税・その他 | 8問 |
宅建試験のメイン科目は、①宅建業法と②権利関係(民法)です。
人によってどの科目を重点的に学ぶのか、得点戦略は異なると思います。
しかし、どのような戦略を取るとしても、試験科目が多くて得点しやすい科目である、①宅建業法の勉強には力を入れる必要があります。
過去の申込者数・受験者数・合格率・合格基準点
| 実施年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格率 | 合格基準点 |
| 2014年度 | 238,343 | 192,092 | 17.5% | 32点 |
| 2015年度 | 243,199 | 194,926 | 15.4% | 31点 |
| 2016年度 | 245,742 | 198,463 | 15.4% | 35点 |
| 2017年度 | 258,511 | 209,354 | 15.6% | 35点 |
| 2018年度 | 265,444 | 213,993 | 15.6% | 37点 |
| 2019年度 | 276,019人 | 220,797人 | 17.0% | 35点 |
| 2020年度(10月) | 204,163人 | 168,989人 | 17.6% | 38点 |
| 2020年度(12月) | 55,121人 | 35,261人 | 13.1% | 36点 |
| 2021年度(10月) | 256,704人 | 209,749人 | 17.9% | 34点 |
| 2021年度(12月) | 39,814人 | 24,965人 | 15.6% | 34点 |
| 2022年度 | 283,856人 | 226,048人 | 17.0% | 36点 |
宅建試験に合格するためには、7割の得点がボーダーラインとなると考えておきましょう。
私が考えるところ、宅建試験に確実に合格するためには、①宅建業法(20問)は満点を目指して勉強することが必要と考えています(実際には最低18点のつもりで計算しておきます)。
残り30問については、真面目に勉強していれば、四択の試験においては二択まで絞ることができるはずです。すると、30問中15問は得点できる計算ですと、
18点+15点=33点ということになります。あと少しで合格できる計算です。
民放が苦手な人は民法に力を入れるべきでしょうし、ある程度民法を理解できている人は、③法令上の制限について力を入れて勉強するべきでしょう。
登録講習を受講した場合
登録講習とは、国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する講習です。登録講習を受講して修了試験に合格し、登録講習修了者証明書の交付を受けると、5点免除を受けることができます。
すなわち、合格基準点から5点を引いた点数が、登録講習修了者の合格基準点となります。
確実な合格を目指すためには、登録講習を受講しておくべきです。