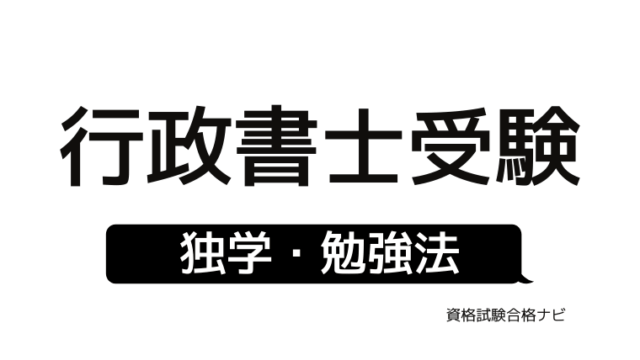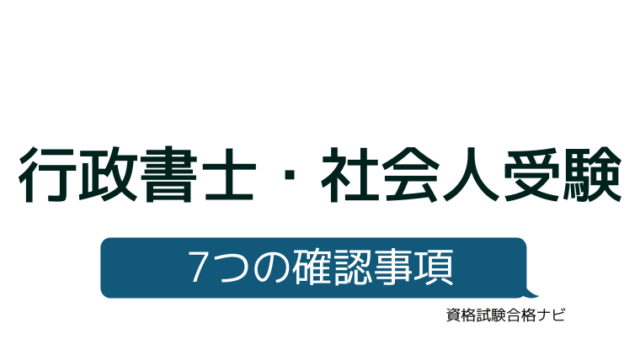- 行政書士になるための3つの方法
- 行政書士試験を目指す際、知っておくべきこと
について書いています。
最初に確認しておきましょう。
目次
行政書士になるための3つの方法
| 第1の方法 | 行政書士試験に合格すること |
| 第2の方法 | 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士の資格を取得すること |
| 第3の方法 | 公務員や特定の独立行政法人の職員として行政事務を20年(高校卒業者は17年)以上経験すること |
行政書士になるには「3つの方法」があります。
行政書士試験に合格することの他にも、弁護士等の難関資格に合格することで行政書士の資格を取得することができるのです。
案外知られていないことは、公務員等として経験を積むことでも行政書士の資格を得ることができること。
行政書士試験に合格することが、最もスタンダードな方法です。他の資格を取得したり、公務員等になることでも行政書士になることができる点についても確認しておきましょう。
なお、行政書士として開業するためには、日本行政書士会連合会に登録する必要があります。

スタンダードな方法は「行政書士試験」に合格すること
| 行政書士試験・出願者(目安) | 5万人〜7万人 |
| 合格者(目安) | 4000人〜6000人 |
| 合格率(目安) | 10%前後 |
| 合格までの勉強時間(目安) | 講座受講 600時間 独学 800〜1000時間 |
行政書士になる、基本的な方法は「行政書士試験に合格すること」です。
行政書士試験は誰でも受験できる試験なので、試験に合格することが多くの人にとって、行政書士になれる最短ルートと言えます。
行政書士試験は、毎年1回実施され、合格する方は4000人を超えます。
行政書士になるには試験合格後に行政書士登録する必要がありますが、登録するには費用(30万円程)がかかることもあり、独立開業しない方は登録しないことが多いようです。
しかし、行政書士に合格したということは社会的に評価されますし、独立開業しないまでも法律的素養があることを証明するものとして履歴書に書くこともできます。

行政書士資格試験の実施概要・内容
| 合格基準 | ① 法令等科目の得点が、122点以上(5割以上) ② 一般知識等科目の得点が、24点以上(4割以上) ③ 全体で180点以上(6割以上) 上記3つを全てクリアすること | |
| 試験科目 | ○法令科目 | 基礎法学、憲法、民法、行政法、商法・会社法 |
| ○一般知識等 | 政治・経済・社会、情報通信、個人情報保護、文章理解 | |
行政書士試験では、大きく分類して「法令科目」と「一般知識科目」があります。
合格基準も細かく分類されており、全ての基準をクリアすると合格判定をもらえることになります。
合格基準点を突破すれば合格できるので、行政書士試験は「絶対評価」の試験ということになります。
行政書士試験に合格するには⇒勉強時間
| 合格率(目安) | 10%前後 |
| 合格までの勉強時間(目安) | 講座受講 600時間 独学 800〜1000時間 |
行政書士試験は受験資格がないので、だれでも受験できる試験ですが、例年の合格率は10%前後です。
受司法書士試験や司法試験の受験生も、行政書士試験を受験することが多いので、受験生のレベルは決して低くはありません。
しかし、合格基準を越えれば合格できる絶対評価の試験ですので、受験対策をした上で勉強することで合格することは十分可能な試験だと思います。
行政書士試験の合格までに要する時間は、人それぞれ異なりますが、正しい方法で勉強している限り600時間〜1000時間で合格できることが多いでしょう。
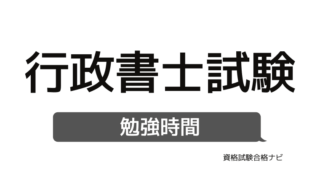
行政書士試験の難易度(他の資格試験とも比較)
行政書士試験の難易度は低いとは言えませんが、高いわけではありません。
法律の基礎学力がある方であれば簡単に合格できてしまう可能性がありますが、法的知識がない方にとっては難しく感じてしまうことが多いようです。
行政書士試験の難易度について、よく比較される試験との対比も確認しておくと良いでしょう。
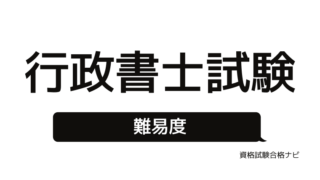
宅建士試験と比較
宅建試験の合格率は「15〜17%」程度ですし、合格までの目安勉強時間は「300時間」程度です。
合格率と勉強時間からみると、行政書士試験は宅建試験よりも難易度が高いと言えます。
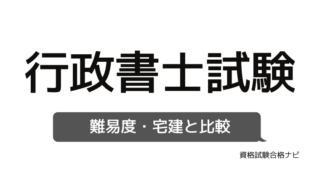
社労士試験と比較
社労士試験の合格率は「2〜7%」程度であり、合格までの目安勉強時間は「1000時間」程度です。
これらからすると、行政書士試験は社労士試験よりも難易度が低いと言えそうです。
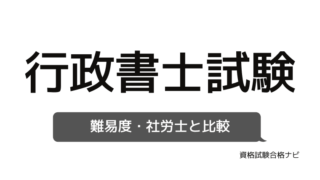
FP検定試験との比較
FP1級試験の合格率は「12%」程度であり、合格までの目安勉強時間は「400〜600時間」です。
このことだけからすると、行政書士試験はFP1級試験よりも難易度が高いとも言えます。

簿記検定試験との比較
簿記1級試験の合格率は「10%」程度であり、合格までの目安勉強時間は「600〜1000時間」です。
簿記1級は相対評価の試験であり、行政書士試験は絶対評価の試験であることを考えると、行政書士試験は簿記1級よりも難易度が若干低いと言えそうです。

司法書士試験との比較
司法書士試験の合格率は「3%」程度であり、合格までの目安勉強時間は「2000〜3000時間」です。
行政書士試験は司法書士試験よりも難易度が低いです。
独学可能?行政書士試験に合格するには
行政書士試験の合格を目指す際は、「独学」学習するか、「講座」を受講するかという方法を選ぶことになります。
行政書士試験の概要を知るために、受験当初に「独学」を選択することは合理的でしょう。まずは勉強を始めてみて、自分との相性や適性を図ることは適切な選択だと思います。
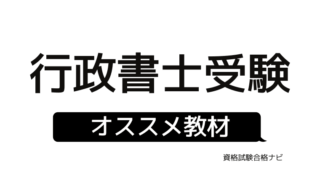
しかし、本格的に合格を目指す場合には、独学での学習はあまりお勧めできません。学習効率が悪いので勉強時間が増える傾向にあります。
「独学で合格した」という人も多いですが、その意味するところは完全なる独学ではなく通信講座やオンライン講座をうまく活用して自学自習で勉強したということが実際のところでしょう。
オススメの「行政書士試験対策」講座
行政書士試験の合格を目指す場合には、通信講座・オンライン講座・通学制講座のいずれかをうまく活用しながら勉強することをお勧めします。
自分が一番適している講座を選ぶことが重要です。
| 良い点 | 注意すべき点 | |
| 通学制講座 | ・受験仲間ができることも ・強制的に勉強機会が ・先生に質問できることも | ・学費が高額になりがち ・受け身の勉強になりがち ・マイペースで勉強できない |
| 通信制・オンライン講座 | ・学費が安い ・マイペースで勉強できる ・大抵、質問サポートもある ・勉強仲間機能があることも | ・自学自習が前提 ・講座により合格率が異なる ・講師・教材との相性が重要 |
具体的に、どの講座を受講すれば良いかは、人により異なります。
「合格率が高い講座」
「講座料金が安い講座」
「教材がわかりやすい講座」
「人気講師の講座」
という視点から講座選びをすることが基本的だと思いますし、
その他にも「短期一発合格を目指せる講座」という観点から選ぶ方もいます。
自分なりの視点で納得のいく講座選びをしましょう。
▼こちらでオススメの講座ランキングを確認できます▼
https://7korobi-8oki.com/shikaku-exam/administrative-scrivener-popular-courses-ranking/
中卒・高卒でも行政書士になれるのか?
行政書士試験には受験資格がないので、中卒・高卒の方でも受験することが可能です。
しかし、実際に合格するには、やはり勉強するしかありません。
中卒・高卒の方の中には、これまで受験勉強の経験が乏しい方もいるかもしれません。勉強のやり方や学習習慣が身についていないという場合には、やはりそれなりに努力することは必要です。
独学で勉強することはお勧めしません。
勉強のやり方や、学習ペースを保つためにも、通信・オンライン講座を受講すると良いと思います(通学制だと出席しただけで満足してしまい、勉強したつもりになるリスクがあります)。
https://7korobi-8oki.com/shikaku-exam/administrative-scrivener-popular-courses-ranking/
行政書士に合格しやすい大学の学部は?
行政書士試験は法律系の科目が多いので、法学部の方には馴染みがある試験でしょう。
受験への抵抗感が少ないという意味では法学部出身の人は合格しやすいと思いますが、他の学部の方でも十分に合格することが可能です。
公務員が行政書士になれる特認制度
行政書士法では、第2条で、公務員として通算17年以上(中卒は20年以上)勤続することを条件として、公務員の行政書士登録を認める「特認制度」を設けています。
行政書士試験と公務員試験の出題範囲には共通項が多いことがその理由として挙げられるようです。
なお、公務員は兼業禁止規定があるので、公務員に在職中に行政書士登録することはできません。しかし、退職した後に行政書士登録をする方は一定数いらっしゃるようです。
湯川七八貴
資格試験受験生のために情報発信を続ける予備校講座の専門家。行政書士試験の合格者からの毎年多くのアンケートを集計し、また各予備校・通信講座の担当者から最新情報を入手するとともに、定期的に情報確認。情報の正確性に注意している
\合格可能性をUP!/
 行政書士には多くの試験対策講座が用意されています。その中には良い講座もあれば、悪い講座もあります。しっかりと見極めて、納得いく講座を選ぶことが重要です。
行政書士には多くの試験対策講座が用意されています。その中には良い講座もあれば、悪い講座もあります。しっかりと見極めて、納得いく講座を選ぶことが重要です。