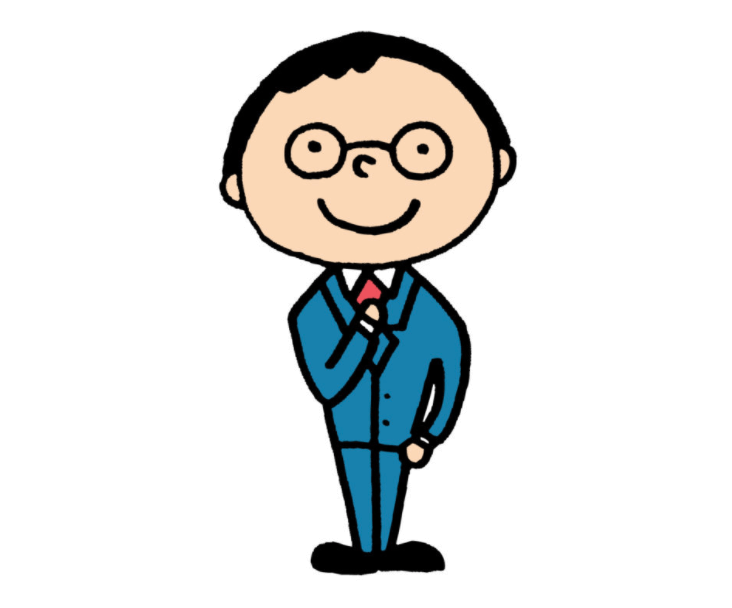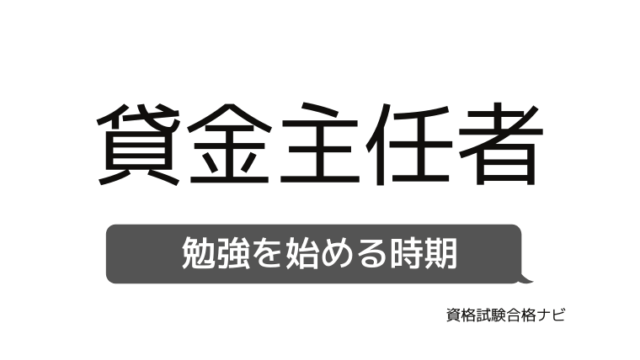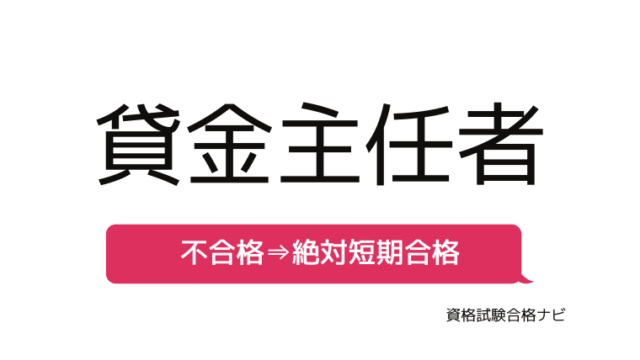次の「貸金業務取扱主任者」試験に合格するための試験対策、攻略法についてです。
「貸金業法および関係法令」の試験対策
試験対策・勉強する際に気を付けること
貸金業法および関係法令の試験科目からは「22~28問」の問題が出題されます。この試験科目(貸金業の法令)の問題について、8割9割を得点できれば合格が見えてきます。
重点的に勉強すべき科目は「貸金業法および関係法令」です。
以下の出題蓋然性が高い項目(◎)をみると、全項目から出題されることが解ります。学習範囲は絞らずに、全項目のマスターを心がけましょう。
学習する際には、全体像をイメージすることが重要です。基本となる考え方について、分かり易くまとまった講義を受講して、理解に努めると良いでしょう。
インプットの際には、あまり細部に入りすぎないことが重要です。
いんぷっとが終わったら過去問演習を通じて具体的な考え方や知識について学ぶ姿勢が重要です。
| 項目 | 出題蓋然性 |
| 貸金業法の目的・定義 | ○ |
| 貸金業者 | ◎ |
| 貸金業務取扱主任者 | ○ |
| 業務運営措置・禁止行為 | ○ |
| 広告・勧誘に関する規制 | ○ |
| 返済能力を超える貸付けの防止 | ◎ |
| 書面が関わる事項 | ◎ |
| 取り立てに関する規制 | ◎ |
| 指定信用情報機関 | ○ |
| 貸金業協会 | ○ |
| 監督および罰則 | ○ |
| 利息および保証料 | ○ |
| その他 | ◎ |
貸金業法関連の問題を解く際に、気を付けること
「貸金業を営む者」の業務の適正な運営の確保および「資金需要者等」の利益の保護を図る点にあります
貸金業法の問題は、過去問をよく学ぶことで理解が深まります。本試験では過去問の練り直しのような問題も多く出題されます。
初見の問題が出た場合には、貸金業法の目的から考えて常識的に判断してみると、正解に辿りつき易くなります。
常識的に判断して間違った問題は、何度も考えながら解き直し、試験直前に見直すと良いでしょう。
出資法・利息制限法関連の問題を解く際に、気を付けること
利息、遅延損害金(賠償額の予定)の問題を解く際には、各法律の違いを意識して解くと、すんなりと解くことが可能になります。
| 利息制限法 | 制限利率を超える利息(遅延損害金)について、その超過部分を無効にする法律 |
|---|---|
| 出資法 | 制限利率を超える場合に、刑罰を科する法律 |
| 貸金業法 | 一定の利率を超える利息で契約した場合に、契約全体が無効となる法律 |
「貸付に関する法令と実務」の試験対策
試験対策・勉強する際に気を付けること
| 項目 | 出題蓋然性 |
| 民事法(民法、電子契約法、商法・会社法、手形小切手法、電子債権記録法等) | ◎ほとんどが民法からの出題です。 |
| 民事手続法(民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、民事調停法等) | |
| 倒産法 | |
| 刑事法 |
貸付に関する法令と実務の問題は、毎年14〜18問の問題が出題されます。この試験科目において、出題ウエイトのほぼ全てを占める言ってもいいいのが民法です。
一口に民法と言っても、出題される分野は一部分です。また、条文知識を問う問題よりかは、事例問題形式での出題が多いので、具体的な場面を想定しながら勉強すると良いでしょう。
基本的な理解が事例を通して出来てさえいれば、正解にたどり着ける問題が多いことも特徴的です。貸金業務取扱主任者の試験をよく研究している教材で学ぶと効率的だと思います。
絶対合格したい方は、民法以外の科目は、ひとまず置いておいて、民法で7割程度得点するつもりで勉強すると良いでしょう。
貸付に関する法令と実務の問題を解く際に、気を付けること
民法の事例問題は、図式化してみると分かりやすく、頭に入り易くなります。
まずは、貸金業務取扱主任者試験の民法講義で、ざっとイメージを固めた後に、過去問演習を積むことです。過去問で学ぶことが効果的な勉強法です。
「誰の誰に対する話なのか」
「どのような権利・義務が問題になっているか」
「契約は有効か」
「相手型は悪意か善意か、善意無過失か」
ということに気をつけて過去問を解いていきましょう。
「資金需要者等の保護」の試験対策
試験対策・勉強する際に気を付けること
| 項目 | 出題蓋然性 |
| 個人情報保護法 | ○ |
| 消費者契約法 | ○ |
| 景品表示法 | ○ |
| 貸金業法等 | ◎ |
資金需要者等の保護の試験科目においては、個人情報保護法、消費者契約法、景品表示法、貸金業法等の分野から「4問〜6問」の問題が出題されます。
特に、貸金業法等については、「貸金業法および関係法令」の試験科目と、出題が重なります。
総量規制の問題は特に得意科目にしておくと良いでしょう。
資金需要者等の保護の問題を解く際に、気を付けること
「貸金業法および関係法令」の試験科目においてもお話ししましたが、とにかく過去問を解くこと。過去問で学ぶ姿勢が大事です。
貸金業法の問題は、過去問をよく学ぶことで理解が深まります。本試験では過去問の練り直しのような問題も多く出題されるのです。
絶対に試験に合格したい方は、この分野においては、まずは貸金業法を完璧にマスターすることを心がける勉強をするようにしてください。
個人情報保護法、消費者契約法、景品表示法については、過去問で出題された範囲で押さえておけばとりあえず必要十分です。
「財務および会計」の試験対策
試験対策・勉強する際に気を付けること
| 項目 | 出題蓋然性 |
| 家計収支の考え方 | |
| 個人の所得と関係書類 | ○ |
| 企業会計の考え方(企業会計原則) | ○ |
| 財務諸表 | ○ |
財務および会計の試験科目については、毎年「2〜4問」の問題が出題されます。
試験に合格するという観点からは、この試験科目について、じっくり勉強する必要はありません。
資金需要者等の保護の問題を解く際に、気を付けること
絶対に次の試験に合格したい方は、むしろ、この試験科目は勉強しないで、適当にマークするだけの方が学習効率・得点効率を上げるためには良いと思います。
絶対に合格!やっておくべき試験対策
賢明なる皆さんは、貸金業務取扱主任者試験においては、
「貸金業法」
「民法」
が大事であり、この2つを押さえておけば、効率的に得点できることに気がついたと思います。
しかも、過去問の練り直し問題が多く出るため、過去問で学ぶことにより、さらに得点効率が上がることも理解していただけたかと思っています。
試験に合格するためには、1年前から勉強するにしろ、直前期から勉強を始めるにしろ、やる勉強に変わりはありません。
「貸金業法」と「民法」の勉強を過去問で学びましょう。
まずは、ざっと全体を予備校の講義で聞いてから、過去問演習を繰り返すと良いと思います。
いつでもどこでも効率よく勉強するために、オンライン教材を使うとより合格が近づいてくるはずです
\無料体験受講ができる/
スタディングを利用すれば、スマホやPC上で、いつでも勉強が出来るし、安心して試験当日を迎えることが可能になります。
是非、無料体験受講をしてみてください。

\スタディング/

会社命令で貸金業務取扱主任者を受験することに。
忙しい中、でも絶対に合格しなければならなかったので、
確実に合格したかった。低コストだったのもスタディングを選んだ理由でした。