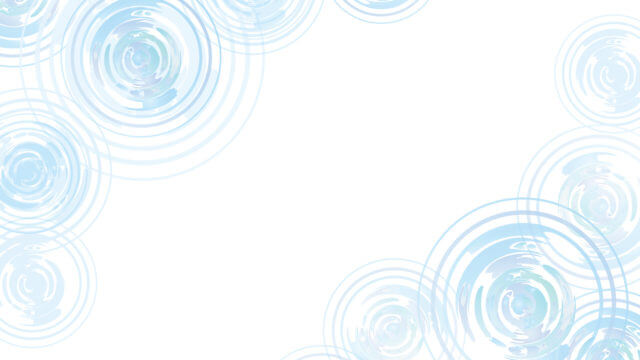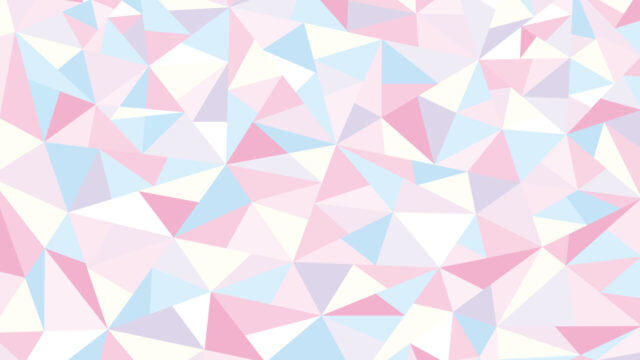私の宅建試験は、受験1年目は「1点」足りずに不合格。
2年目は「1点」クリアで合格でした。不合格から合格までの、1年間に気を付けたことをご紹介します。

目次
宅建試験不合格からリベンジ合格⇒①来年合格の自覚を
「合格するのは自分だという自覚を持つ」
宅建の試験を受ける前年、某資格学校で、別の資格試験に合格した私は、資格学校にお金さえ払えば合格させて貰えるという勝手な誤解をしていました。
そして、宅建試験の受験1年目は、同じ資格学校でビデオ講座を受けましたが「1点」足りずに不合格。
このとき、資格学校や通信教育は合格のため、回り道をしないように案内はしてくれるけど、あくまでも合格するのは自分だとういことを痛感したのです。
翌年は「合格するのは自分」という自覚を持って勉強出来たことが、合格に一番役立ったことでした。
宅建試験不合格からリベンジ合格⇒②出来ない言い訳禁止
「言い訳をしないこと」
宅建試験に不合格者からは、よく「忙しくて勉強する時間がない」という弱音を耳にすることがあります。
忙しくて勉強する時間が無かったからといって、試験本番では加点してくれません。
宅建試験に合格するかしないかは、「やるかやらないか」です。
試験会場に100人いたら80人以上の人が不合格になる試験です。本当に合格したいのか?合格する気はあるのか?
私の場合、常に自分に問いかけていました。

宅建試験不合格からリベンジ合格⇒③何度も繰り返し学習
「何度も繰り返し読む・問題を解く」
私の場合、受験1年目は資格学校のビデオブースで眠くなりながら、歯抜け状態でようやく一通り勉強したという程度でした。
ですが、資格学校(通学、オンライン)、通信教育、参考書、どのような教材で勉強したとしても、合格するためには、全てやりきった状態がスタートラインです。
スタートラインと言ったのは、一度理解したり、覚えても、しばらくすれば忘れてしまいまうので繰り返しが必要だということです。
私は1年目に不合格になってから、ある合格者のエピソード読みました。
『宅建の試験勉強で同じ本を最初に5冊買って1冊がボロボロになったら次というのを繰り返して5冊やって合格した』とありました。
それだけ勉強すれば、そりゃ合格するでしょ。大事なのは同じものを何度も繰り返すということでした。
私も2年目は通勤電車の中だけでも、毎日往復2時間半はずっと同じ1冊の本を繰り返し読むというスタイルで「1点」クリアで合格したのです。
自分が使っている学習教材を信じて、何度も繰り返すことが大切です。
宅建試験不合格からリベンジ合格⇒④スキマ時間を有効活用
「忙しくても、スキマ時間を有効活用」
受験1年目は、資格学校に通ったり休日も家でみっちり机にしがみついて過去問を解いたりしていました。
ですが勉強自体は、まとまった時間が取れなくても5分もあれば1問勉強するくらいはできます。
1日5分多く勉強することで、1週間では30分多く勉強できます。
私の場合、2年目受験は、通勤の電車だけでなく移動中の電車の中や、外出でアポの時間の30分前に早めに現地周辺に到着して近くで、コーヒーを飲みながらの時間などスキマというスキマ時間の活用をしました。

宅建試験不合格からリベンジ合格⇒⑤満点不要・合格点を意識
「満点は不要、合格に必要な守備範囲をハッキリさせる」
1年目は満点を取るつもりで勉強したのですが、逆に穴だらけになってしまいました。
例えば、用途地域の問題などは建築士試験では法令集を持ち込んでも手間がかかる問題です。なのに、宅建試験では暗記していなければいけません。
よほどの優秀な人でなければ、全てを覚えることは難しいでしょうし、満点を取るつもりで一つの単元だけに時間を掛けすぎるのも学習効率は悪いです。
受験2年目は用途地域の問題も含め、「ここだけは絶対得点する」という暗記の軸を決めました。
暗記の軸が確実なものになったら、少しだけ守備範囲を広げるといった勉強をしたのです。
満点を取る意識でなく、合格点を取るという意識に変えました。
勉強する際に、必ず「得点する」守備範囲をハッキリさせました。
宅建試験の受験生へ(落ちた方へ)
宅建の試験に不合格になったからといって、その人が「頑張らなかった人」とは限りません。
宅建合格率の低さからも、宅建試験は「頑張った人を振るい落とす」試験なのです。
ですが、少しだけ学習意識を変えて、合格だけに意識を切り替えるだけで合格できる試験でもあります。
以上、1年目不合格だった私と、2年目の合格した私を比較する形でお伝えしました。
皆さんが来年合格するためのヒントにしていただけたら幸いです。

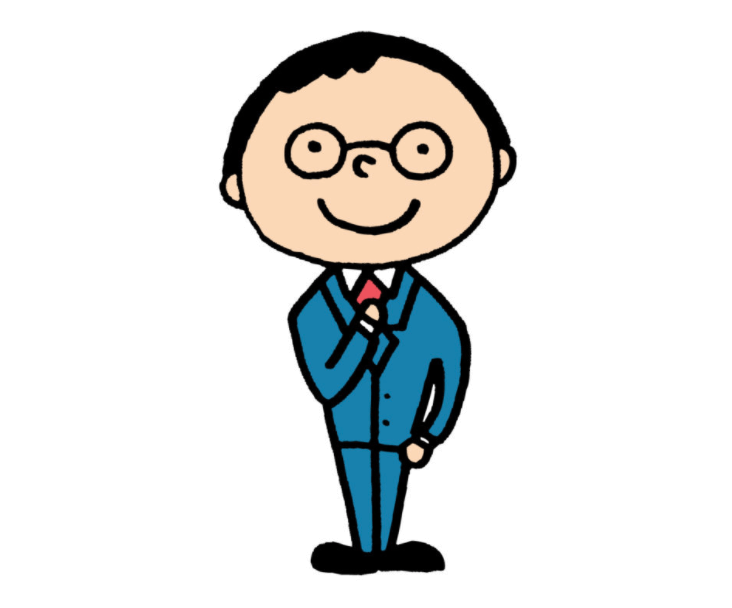 ◆
◆