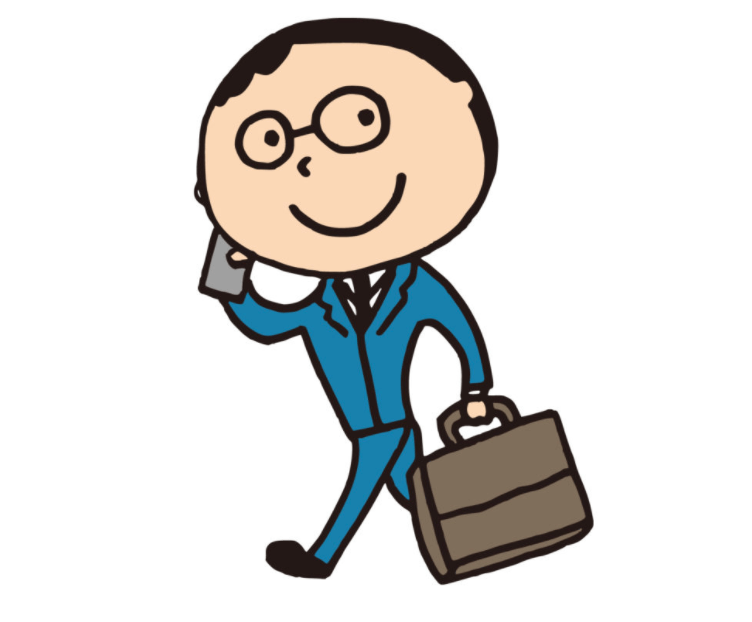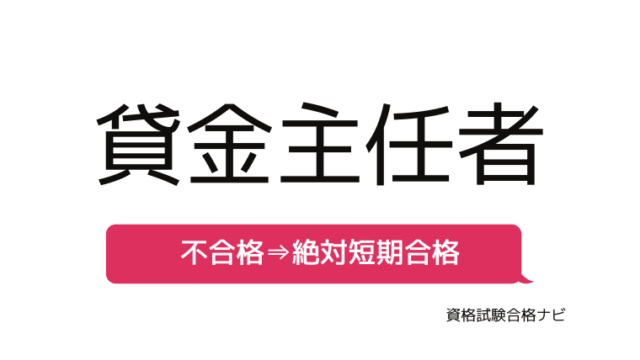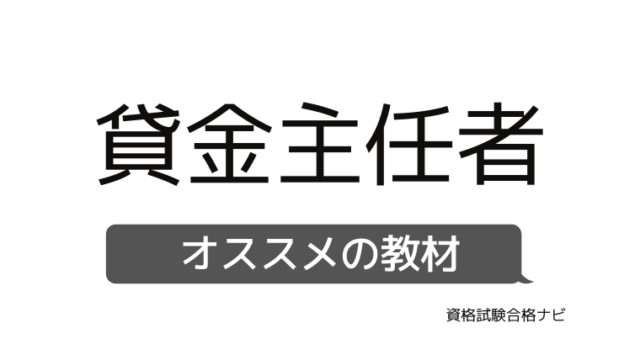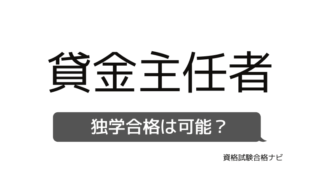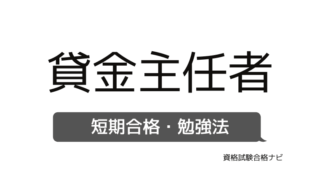貸金業務取扱主任者の資格試験は、難易度が低いと誤解している人がいます。
でも、試験問題の内容は難しいので、不合格になる人が毎年多数います。
合格するためにはいつから試験勉強を始めるべきなのか?順を追ってお話しします。
目次
そもそも貸金業務取扱主任者の資格試験に合格することは難しいのか?
貸金業務取扱主任者の資格試験の出題範囲は広範囲にわたります。
合格者の中には、「試験問題は簡単だよ」という人もいますが、本当でしょうか?
私は決して簡単とは思いません。
試験で問われている内容を正確に理解するためには、並大抵の勉強・努力では足りません。
でも、ただ単に、
貸金業務取扱主任者の試験に「合格すること」だけを目的にするならば、そこまで深く正確な理解は必要ではありません。
「合格すること」だけを単純に考えるのであれば、この資格試験は合格レベルがそれ程高いとまでは言えないでしょう。
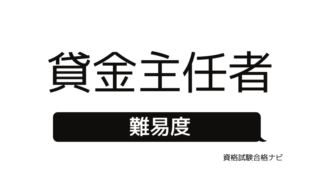
試験に合格する為に押さえておくべき出題範囲
では、貸金業務取扱主任者試験に合格するためには、どの出題範囲を解けるようにしておかなければ行けないのでしょうか?
試験に合格するために、どの範囲、どの問題が解けなければいけないのか、明確に把握する必要があります。
貸金業務取扱主任者の試験合格を意識するのであれば、
①貸金業法関連
②民法
の問題を、確実に解けるようにしておく必要があることを押さえておきましょう。
あえて言い換えてみると、
①貸金業法関連と、②民法だけをしっかり勉強することが大事です。
特に貸金業法について、確実な理解と知識で準備しておけば、必ず合格できると思います。
貸金業法関連についても、出題範囲の全てを勉強して、マスターする必要はありません。
たとえ知らない問題が出題されたとしても、「借主保護」という視点さえ持っていれば、正解にたどり着くことができる問題が多いです。
だから、「借主保護」の視点で解くことができない問題や知識について、絞り込んで勉強すると良いでしょう。
民法については、貸金業務取扱主任者の資格試験では、いわゆる条文知識のみが出題されます。
試験には判例問題や事例問題は出題されません。
しかも出題される分野にも偏りがあるので、やはり民法についても絞り込んで勉強する必要があります。
貸金業務取扱主任者に合格するための試験勉強はいつから始めるべき?
試験勉強を開始する時期は、「民法」の学習経験の有無により異なります。
民法の学習経験について、場合を分けてお話しします。
民法の学習経験がある人の場合
民法の学習経験がある人の場合、ある程度ゆとりを持って勉強を始めても良いでしょう。
もちろん、受験勉強を始める時期が早いことに越したことはないのですが、早く勉強を始めたからと言って必ず合格できるわけではありません。
「合格するために必要な学習範囲を見極めること」
「効率学習に役立つ学習教材を利用すること」
この2つが合格するために必要最小限の前提となりますが、
既に民法の知識がある人は、残りは「貸金業法関連」の勉強に特化して、集中して勉強することで足りるので、受験勉強に要する時間は、若干少なくて済むと思います。
試験勉強はいつからするべきか?は、どのような試験勉強教材を使うのか?ということに関連するのですが、
- 要点が解りやすく書いてある教材
- 隙間時間で勉強できる(スマホでも勉強できる)教材
で学ぶのであれば、それほど時間は要りません。
5月のGW頃から徐々に準備を始めることが理想的です。
でも遅くても、試験の2ヶ月前からは、ある程度の本腰を入れて勉強をはじめて欲しいところです。
ただ仕事が忙しかったりして、勉強時間の確保が難しい場合には、最低「試験の1ヶ月前」には真剣に勉強するようにしてください。
わたしの場合も、本格的に試験勉強を始めたのは「試験の1ヶ月前」でした。
民法の知識はあったので、貸金業法に特化して勉強して合格水準に達することが出来たのです。
私のメインの勉強場所は「電車の中」などの隙間時間がとれる場所でした。電車で座っているときでも、電車で立っているときでも繰り返し、スマホで勉強していたのです。
(仕事が忙しかったので受験勉強のスタートが遅れてしまいました。直前1ヶ月前からの勉強は流石に大変でした。出来ればもう少し早く学習スタートすることが良いでしょう)
民法の学習経験がない人の場合
一方、民法について基礎知識が十分でない人は、もう少し前から、余裕をもって勉強を始めることをオススメします。
貸金業務取扱主任者の資格試験で出題される民法知識は、条文知識レベルなので、それほど難しい勉強は必要ではありません。
試験の出題範囲は限られています。
しかし、民法の基礎知識がない人にとっては、法律の勉強は大変です。少なくとも、民法だけで3、4ヶ月間の学習期間が必要です。
貸金業法関連と民法の勉強とで合わせて、理想的には受験年度の1月から、どんなに遅くても5ヶ月前からは本腰をいれた勉強が必要だと思います。
オンライン上で勉強できる、解りやすい教材を使って勉強することが重要です。オススメは「スタディング」という教材です。

スタディングを利用すれば、スマホやPCから、いつでも勉強することも出来るので、電車の中でも会社PCからでも、勉強することができます。
いつから試験勉強をするべきなのか?確認できたら、次は「試験に合格するための勉強法」についてお話ししておきたいと思います。
貸金業務取扱主任者の資格試験に合格するための勉強法
勉強法1:資格試験の勉強時間を十分に取れる人
受験勉強のために、勉強時間をある程度確保できる場合には、腰を据えて、しっかりと勉強するべきです。
ただ、いくら時間があったとしても、全ての出題範囲広いので、全範囲を学習することは不可能だと考えておきましょう。広く深く勉強することは難しいと考えてください。
試験に合格するためには、完璧主義はNGです。真面目な人ほど合格することが難しい試験です。
完璧主義に陥って、緻密な勉強を始めてしまうと、試験合格から遠のいてしまうことでしょう。
どの資格試験についても同じことが言えますが、資格試験に合格するには、必要な勉強範囲を絞って、合格に必要となることだけを効果的に勉強することが必須です。
効率的な学習を心がけること。メリハリをつけて、勉強の強弱をつけることです。
独学で合格することは難しいので、効率的な勉強をするために、スタディングのように合格者に評判が良い教材を利用すると良いでしょう。
勉強法2:資格試験の勉強時間を取れない人
仕事が忙しかったりして、受験勉強の時間を確保できない人は、より一層「試験に出題されるポイント」に絞って学習する必要があります。
講座を受講して、隙間時間を有効的に使うことです。
- 電車に乗っている時間
- 待ち時間
- トイレに入っている次官
- 寝る前の時間
ちょっとした時間でいいので、絶え間なく勉強する生活環境づくりに励んでください。
その為に、隙間時間で勉強することができる、効果的な信頼あるオンライン教材を使いましょう。
多くの方は、会社の業務に必要だったり、会社の命令で受験していることと思います。
「失敗できない、不合格にはなれない」
「必ず合格しなくてはいけない」
そんなプレッシャーがあることでしょう。
試験に必ず合格するために、学習環境を整えましょう。
時間がない人はとりわけ「勉強教材選び」に神経を使うことが大事です。
- 要点が解りやすく書いてある教材を選ぶこと
- 隙間時間で勉強できる(スマホでも勉強できる)教材を選ぶこと
これが試験に合格するために、必須ポイントとなります。
▼オススメの教材▼

スタディングは貸金業務取扱主任者の試験勉強に最適な教材です。
特に会社命令で受験する方は、確実に合格するために万全な準備をしておくべきです。
\スタディング/

会社命令で貸金業務取扱主任者を受験することに。
忙しい中、でも絶対に合格しなければならなかったので、
確実に合格したかった。低コストだったのもスタディングを選んだ理由でした。