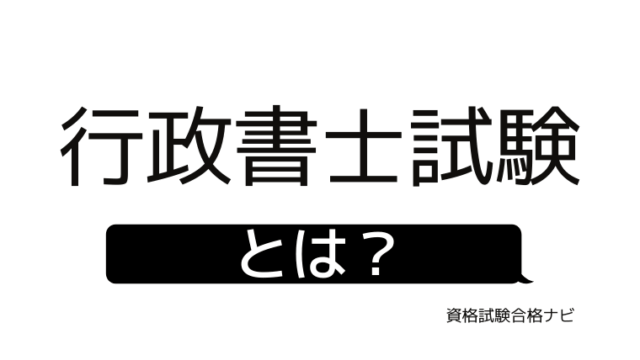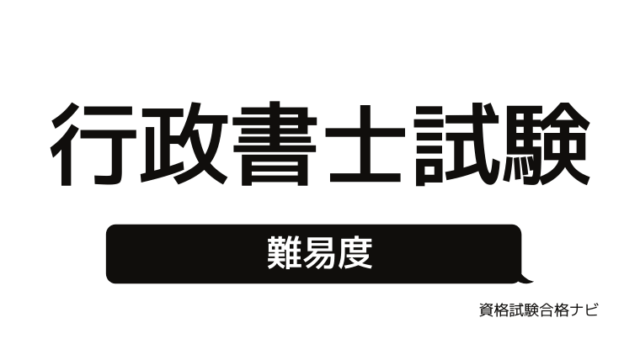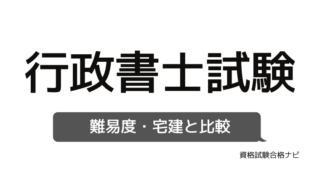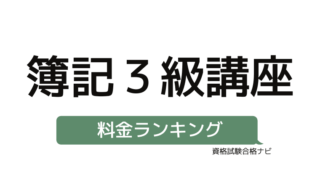目次
行政書士と社労士の違いは?(業務内容と年収、合格率)
あまり知られていませんが、行政書士と社労士は、そのむかし同じ資格でした。
しかし、戦後の高度成長に伴い、会社の数が増えて規模も大きくなった結果として、社会保険に関する業務が複雑化したことに伴って、1968年に社会保険労務士という資格が生まれたのです。
業務内容の違い
| 行政書士 | 主に行政機関のに対する許認可申請手続き等 | 飲食店営業許可、建設業営業許可、定款作成、車両登録、遺言書作成など、 |
| 社労士 | 保険や年金、労務管理のプロフェッショナル | 健康保険や年金、雇用保険などの手続きに関する書類の作成代行、企業の労務管理など |
行政書士、社労士ともに、法律手続き等に関する書類作成や、手続代行をしたり、専門知識に基づくアドバイスを行いますが、
行政書士は「行政機関に対する各種許可申請」の書類申請や提出代行などを主な業務として行っています。その他にも遺言書の作成や、争いになっていない相続相談にのる業務、契約書等の代理作成業務なども行っています。
一方、社会保険労務士の業務範囲は「保険・年金・労務管理」です。例えば、健康保険や厚生年金の金額を計算するのが社労士が独占業務として行う仕事です。また、労働管理について会社にアドバイスをして改善指導する役割も担っています。
平均年収の違い
| 一般的には | 実務経験 | |
| 行政書士 | 300〜600万円 | 個人の働き方により差がある |
| 社労士 | 530万円程 | 厚生労働省による賃金構造基本統計調査・給料BANKの統計参照 |
本試験合格率の違い
| 合格率 | 実務経験 | |
| 行政書士試験 | 10〜15%程度 | 不要 |
| 社労士試験 | 2〜7%程度 | 合格後、実務経験2年以上または指定講習修了 |
本試験の合格率を見ると、社労士試験の方が合格率が低いことがわかります。
それに、社労士試験の場合は、社労士として登録するには、国家試験に合格後、実務経験等が必要となるのです。
合格に要する勉強時間は?(行政書士・社労士試験)
| 行政書士試験 | 600〜800時間(目安) |
|---|---|
| 社労士試験 | 1000時間(目安) |
行政書士試験と社労士試験において、一般言われることが多い勉強時間の目安を記載してみました。
あくまでも合格するために必要となる目安の勉強時間です。実際の学習時間は人により異なりますが、いかがでしょうか。
試験の合格率(難易度)に比例して、受かるために要する勉強時間にも違いが出ているようです。
この勉強時間は、予備校に通ったり通信講座を受講していることが前提となるので、独学で勉強している方はもう少し勉強時間が増加しそうです。
難易度は?行政書士と社労士はどっちが難しい?
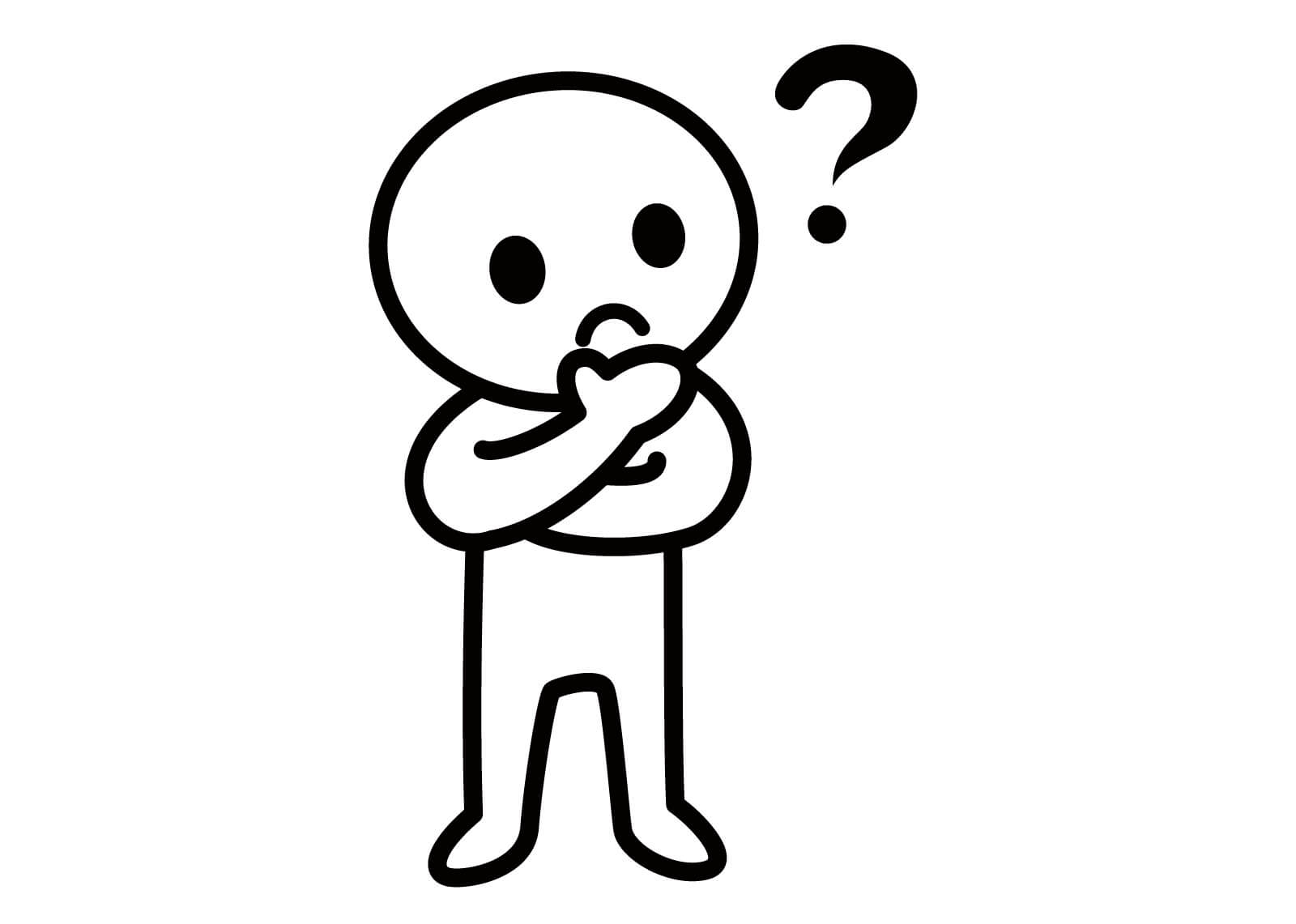
行政書士試験に合格するのと、社労士試験に合格するのでは、どちらが難しいといえそうでしょうか。
① 合格率が低いのは「社労士試験」
比較することは難しいですが、合格率だけを見ると「社労士」試験の方が合格率が低いですから、社労士試験の方が難易度が高そうです。
② 勉強時間の目安が多いのも「社労士試験」
それに合格までに必要となる勉強時間の目安でも、社労士試験の方が行政書士試験を大きく上回っています。
社労士に受かるまでの労力も社労士試験の方が多いです。
③ 合格基準が厳しいのも「社労士試験」
行政書士試験も社労士試験のいずれも、本試験においては合格基準が設定されています。
しかし、社労士試験の場合は「科目ごと」の合格基準が設定されているのに対して、行政書士試験の場合はそこまで詳細な合格基準は設定されていません。科目ごとの合格基準は設定されていないのです。
「合格基準」制度に注目した場合でも、社労士試験のほうが厳しいのです。
④ 出題範囲には違いがある
行政書士試験と社労士試験においては、出題範囲についても差異があります。
社労士試験んは、労働法関係・社会保障関係という限定された分野に関して「狭く深く」出題されるという特徴があります。
一方、行政書士試験の場合は、様々な分野から広く出題されるのです。「広く浅く」出題されるという特徴があります。
このように両者を一概に比較することは困難ですが、両方の試験について受験経験がある方は「社労士試験の方が難易度が高い」ということが多いように感じます。
結局のところ、社労士試験の方が行政書士試験よりも難易度が高いと言えそうです。
行政書士と社労士試験の同時受験は可能か?
行政書士試験と社労士試験は、いずれも法律系の資格試験と分類されております。
でも、両者は重なる試験科目がないので、どちらかの受験勉強を他の資格試験に活かすことはできません。
ですから、同時期に2つの試験勉強をしてダブル合格を目指すことは、相当難しいといえます。
行政書士と社労士のダブルライセンスを取得したい場合には、一つづつ、順番を追って試験勉強した方が良い。確実に合格を目指せると思います。
一番効率の良いのは、11月に行政書士試験を受験・合格して、翌年8月に社労士試験の合格を目指すというのが、効率よく最短で合格できるスケジュール感だと思います。
ダイブルライセンスのメリットは?(年収など)
行政書士と社労士の資格は、業務領域が異なるので、実際の業務において相互補完できることはありません。
しかし、ダブルライセンスを取得していれば、それだけ仕事の範囲が広がります。
行政書士のお客さんを社労士の仕事に取り込んだり、またその逆のケースも合ったりと顧客開拓の可能性が広がります。
行政書士と社労士、とるならどっち?

就職の観点からは、
行政書士と社労士を「就職面」で比較すると、社労士を取得した方が良いでしょう。
社労士であれば、独立開業できる他にも、社員として働く「勤務社労士」となることができます。就職にも強いという点で、就職に強い資格と言えるでしょう。
しかし、行政書士の求人は少ないので、行政書士としての就職は難しいと言えます。
今後、法律系資格をステップアップさせたいならば、
一方、これから司法書士試験や予備試験・司法試験、法科大学院といった法律系の資格を受験して、ステップアップを目指す方であれば、行政書士試験を受験するべきです。
行政書士試験と司法書士、司法試験においては、重なる試験科目があるので、行政書士試験で勉強した内容を活かすことが可能です。
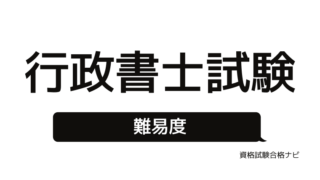
湯川七八貴
資格試験受験生のために情報発信を続ける予備校講座の専門家。行政書士試験の合格者からの毎年多くのアンケートを集計し、また各予備校・通信講座の担当者から最新情報を入手するとともに、定期的に情報確認。情報の正確性に注意している
\合格可能性をUP!/
 行政書士には多くの試験対策講座が用意されています。その中には良い講座もあれば、悪い講座もあります。しっかりと見極めて、納得いく講座を選ぶことが重要です。
行政書士には多くの試験対策講座が用意されています。その中には良い講座もあれば、悪い講座もあります。しっかりと見極めて、納得いく講座を選ぶことが重要です。