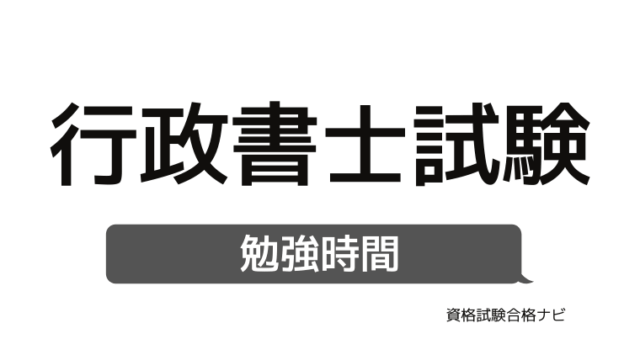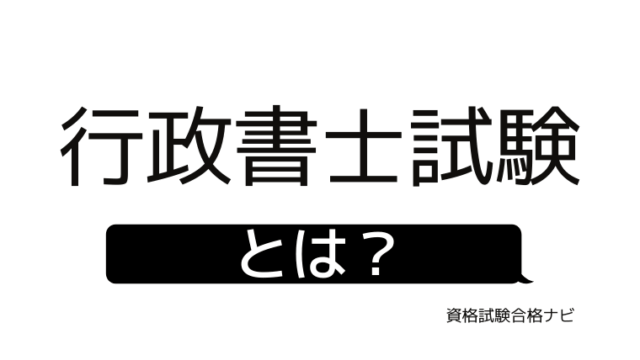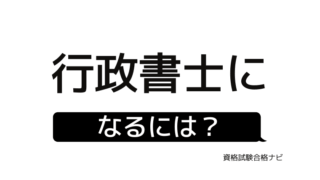目次
行政書士とFP1級2級の違い(比較)
仕事内容の違い
| 行政書士 | 仕事内容 | 許認可等の申請の際に行政機関に提出する書類の作成 (独占業務) 契約書・権利関係の証明に関する書類の作成 |
| 試験科目 | 基礎法学・憲法・民法・行政法・商法 IT情報通信・個人情報保護法 一般知識 | |
| FP | 仕事内容 | 年金や資産運用、保険、住宅ローンなどお金に関するアドバイス |
| 試験科目 | ファイナンシャルプランニング・顧客データの収集と目標の明確化・顧客のファイナンス状況の分析と評価・プランの検討・作成と提示 |
行政書士とファイナンシャルプランナーとでは、「仕事内容」も「試験科目」も異なります。
行政書士は法律に関する資格であり、FPは主にファイナンシャルプランニングに関する資格という違いがあるというイメージを持ちましょう。
平均年収の違い
| 行政書士 | 400〜450万円(目安) |
| FP | 350〜400万円(目安) |
行政書士は主に独立開業したり、事務所勤務することにより仕事をしますし、FPは独立したり金融系に勤務することになるでしょう。
独立している方の場合には、特に個人差がありますが、行政書士の年収の方が若干多いイメージで間違いはなさそうです。
行政書士とFP1級2級の難易度・試験合格率・勉強時間は?
受験資格の観点
| 行政書士試験 | 受験資格は特になし |
|---|---|
| FP1級 | FP2級を取得し、且つ1年以上のFP業務の実務経験 or FP業務で5年以上の実務経験 |
| FP2級 | AFP認定研修を終了 or FP3級に合格 2年以上のFP業務の実務経験 |
行政書士試験においては、受験資格はありません。合格した後は行政書士として登録をする必要がありますが、試験自体は誰でも受験することが可能です。
一方、ファインシャルプランナーの検定試験においては、受験資格があります。
FP試験の方が、受験資格が厳格であるという点において、難易度は高いとも言えます。
試験合格率
| 行政書士試験 | 10%程度 |
|---|---|
| FP1級 | 12%程度 |
| FP2級 | 25%程度 |
一方、それぞれの試験の合格率を見てみると、基本的には行政書士試験の合格率が一番低いことがわかります。
合格率の観点からは、行政書士試験が難関試験であると言えそうです。
合格に要する勉強時間
| 行政書士試験 | 600〜800時間(目安) |
|---|---|
| FP1級 | 400〜600時間(目安) |
| FP2級 | 150〜300時間(目安) |
さらに、合格までに必要となる勉強時間の観点からすると、一般的には、行政書士試験の合格に要する学習時間が一番長いことがわかります。
勉強時間の観点からも、行政書士試験の難易度が一番高いと言えそうです。
行政書士とFP1級2級⇒難しいのはどれ?
結局のところ、行政書士試験とFP検定試験を比べた場合、「行政書士試験」が最も難易度が高いと言えます。
行政書士とFPの合格者も、多くの方が行政書士の方が難しいと言っていることからも、合格者の感覚と合致していると言えます。
ただし、FPの場合には受験資格としての「実務経験」などが必要となるので、この点を捉えてFPの方が資格取得までの時間がかかる傾向にある点は頭に入れておきましょう。
行政書士とFP1級2級の相性はいいか?
行政書士とFPは、仕事内容と試験内容が異なるのですから、それらの点を捉えると重なり合いがありません。行政書士は官公庁に対する書類提出や契約書作成などを主な仕事としますし、FPは個人の生活に関わるお金のことを扱う仕事をしているのです。
しかし、実務において、行政書士とFPの相性が良い場面もいくつか存在します。
例えば、相続に関する業務を考えてみましょう。
家族の誰かが死亡して「相続」が発生した場合、実際の相続に関する手続きについて、行政書士が活躍する場面があります。
行政書士は相続に関する法的手続きについて説明し、必要となる書類作成をする業務を行うことがあります。行政書士はそれ以上の仕事は専門外です。
しかし、相続問題に直面している顧客側の立場としては、相続のまつわるお金の具体的なことも相談する専門家を欲するケースが多いでしょう。
FPであれば相続が起きる前後のお金に関する相談、相続手続きが終わった後の遺族の生活設計相談などをサポートすることができます。
相続などについて、行政書士とFPの資格があれば、異なる分野についてワンストップで対応できるのです。その意味において行政書士とFPの相性は良いと言えるのです。
行政書士とFP1級2級のダブルライセンスのメリットは?
先の相続の例からみてもわかるように、行政書士とFPのダブルライセンスのメリットは大きいと言えます。
顧客から相続に関する相談を受けた場合、
FPとしては、相続にまつわるお金の問題についてプランニングして、関係者に提案することができます。相続の場面では、相続対象となる財産を洗い出しのうえ一覧化して、相続税を計算、不動産売買にかかわるアドバイスなどが主な仕事内容となります。
行政書士としては、関係者の合意形成を進めるために、相続において必要とな以下の書類を作成することができます。
| 相続関係説明図 | 相続人が誰であるかを一目で確認できるようにするために作成される図面 |
|---|---|
| 相続財産目録 | 不動産、動産、有価証券、有価証券など相続財産を一覧にしたもの(概算評価額も含む)。相続人が財産分割する際に利用する。 |
| 遺産分割協議書 | 相続人が財産を具体的にどのように分割するのか、協議結果を書面化したもの。相続人全員が署名・捺印する。 |
依頼者側としてもワンストップで相続に関する相談や実務の依頼をできることは便利ですので、行政書士とFPのダブルライセンスのメリットは大きいと言えます。
行政書士とFP⇒資格を取るならどちら?
ここまで行政書士とFPについて、試験難易度や、仕事内容、ダブライセンスのメリットなどをみてきました。
難易度については、行政書士試験の方がFP検定試験よりも、若干難しいことが解りましたし、
年収については、行政書士の方がFPよりも、若干収入が多そうであることも解りました。
しかし、どちらか一方を選ぶのであれば、自分がやりたい仕事はどちらの方が近いのか?ということを具体的にイメージして選ぶことが一番良いと思います。
どちらの資格でもいいから、とにかく就職したいという方であれば「FP検定」の方が就職に直結しやすい部分もあるかと思います。
行政書士は、どちらかというと独立開業を目指す方に向いている資格と言えそうです。
「やりたいことは何か」
「就職したいのか、独立したいのか」
そのような観点から、まずはどちらかの資格を取得してみるというのが、正しい選び方のように思います。
ご参考になりますように。
湯川七八貴
資格試験受験生のために情報発信を続ける予備校講座の専門家。行政書士試験の合格者からの毎年多くのアンケートを集計し、また各予備校・通信講座の担当者から最新情報を入手するとともに、定期的に情報確認。情報の正確性に注意している
\合格可能性をUP!/
 行政書士には多くの試験対策講座が用意されています。その中には良い講座もあれば、悪い講座もあります。しっかりと見極めて、納得いく講座を選ぶことが重要です。
行政書士には多くの試験対策講座が用意されています。その中には良い講座もあれば、悪い講座もあります。しっかりと見極めて、納得いく講座を選ぶことが重要です。