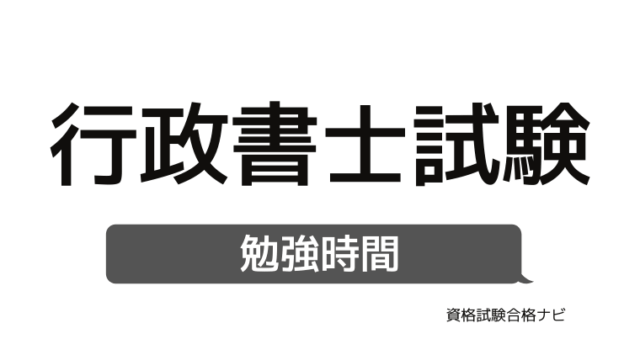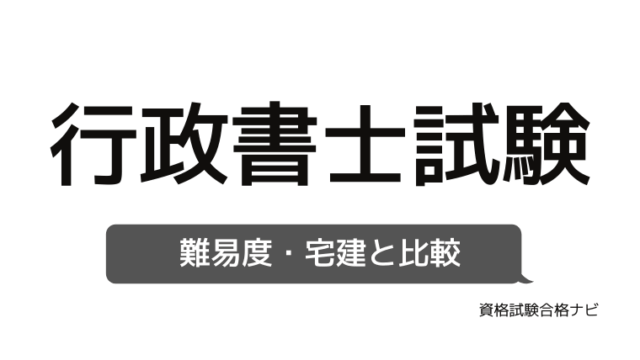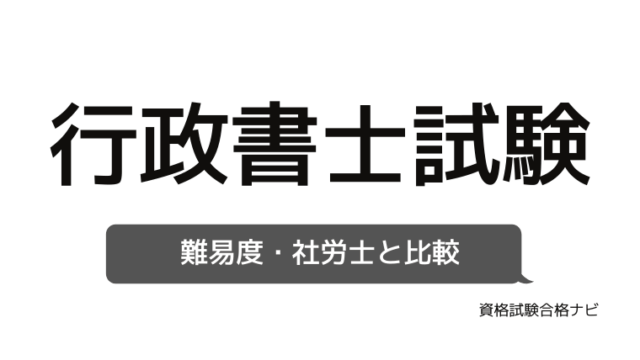目次
行政書士と簿記1級の難易度比較⇒合格率・合格基準
合格基準・合格率の目安
| 資格 | 合格基準 | 合格率の目安 | |
| 行政書士 | 国家資格 | 絶対評価 1:法令等科目で122点以上得点 | 合格率は10%程度 |
| 簿記1級 | 民間資格 | 相対評価 | 合格率は10%程度 |
行政書士の試験合格率は、例年10%前後であるのに対して、簿記1級の検定合格率も例年10%前後なので、数字だけ見ると同じような合格率です。
行政書士試験は絶対評価
しかし、行政書士試験は全体的に6割得点できれば基本的に合格となります(試験問題が極端に難しい年度では、例外的に合格点を下げる補正措置が実施されることも)。
合格基準点を上回れば合格できるので、行政書士は絶対評価の試験と言えます。
簿記1級は相対評価
一方、簿記1級の試験についても合格基準があり、70%以上の得点を取れば合格できるので絶対評価の試験のように見えるのですが、
しかし、簿記1級試験の合格率は例年一定的(10%程度)ですので、実際には合格者数を一定に保つための調整(傾斜配点)が行われていることが伺われます。
傾斜配点が実施されることにより、簿記1級試験は相対評価になっていると言えるでしょう。
合格率が低い場合:正答率が高い問題の配点を大きくして合格率を上げる
合格率が高い場合:正答率が高い問題の配点を小さくして合格率を下げる
簿記1級試験の方が難しい?
行政書士試験が絶対評価の試験に対して、簿記1級は相対評価の試験です。
簿記1級試験は合格基準点をクリアしても他の受験生よりも高得点を取らなくてはならないケースがあるので、簿記1級試験の方が行政書士より難易度が高いように思えます。
合格基準が具体的な点数で事前に決定されていて、合格基準点を取得できれば合格し、そうでなければ不合格となります。
合格基準が「上位○%」というように「受験者数に対する割合」で決定されています。
受験者全体のレベルが高ければ実力があっても合格できないことがあります。
行政書士と簿記2級の難易度比較⇒合格率・合格基準
合格基準・合格率の目安
| 資格 | 合格基準 | 合格率の目安 | |
| 行政書士 | 国家資格 | 絶対評価 1:法令等科目で122点以上得点 | 合格率は10%程度 |
| 簿記2級 | 民間資格 | 絶対評価(70点以上得点) | 合格率は5%強〜50%弱 (大抵30%前後の合格率) |
簿記2級は簿記1級より難易度が低い
簿記2級試験は、簿記1級に比べると、難易度が低くなります。
簿記2級の合格率は、大抵の場合30%前後となりますが、通信講座等を受講している方であれば合格率は80%前後となることが多いでしょう。
独学での合格も可能ですが、勉強時間が長くなったり、学習効率や合格可能性が悪くなりがちです。合格実績の高い講座を受講すると良いでしょう。
簿記2級は行政書士試験より難易度が低い
行政書士試験の合格率は10%程度であり、簿記2級試験の合格率は30%程度です。
試験範囲は異なるので単純比較することはできませんが、合格率の観点からは行政書士の試験の方が簿記2級より難しい試験です。

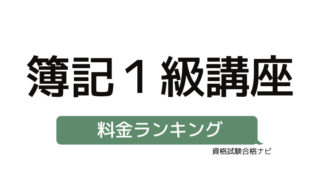
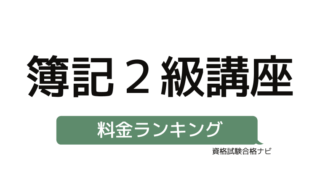
行政書士と簿記1級2級⇒勉強時間から見る難易度比較
| 行政書士試験 | 600〜800時間(目安) |
|---|---|
| 簿記1級 | 600〜1000時間(目安) |
| 簿記2級 | 200〜500時間(目安) |
合格までに必要となる勉強時間の観点から難易度を比較してみます。
上記表にあるように、行政書士試験よりも、簿記1級に必要となる勉強時間の方が長いことがわかります。
勉強時間で比べてみると、以下のような難易度になります。
簿記1級 >行政書士 >簿記2級
行政書士と簿記1級・2級難しいのはどれ?
合格基準(絶対評価・相対評価)の観点と、合格に要する勉強時間の観点からは、簿記1級試験が一番難しいように見えます。
また、受験者層を実質的にみても、簿記1級試験の受験生の中には、会計士受験生と税理士受験の受験資格を得ようとする受験生がかなりの割合を占めています。
会計士試験と税理士試験の受験生のレベルは高めですので、やはり簿記1級試験の合格率が一番高いように思います。
簿記1級 >行政書士 >簿記2級
試験の難易度別に並べてみると、やはり
「簿記1級」
「行政書士」
「簿記2級」
という順番になるという理解が正しそうです。
行政書士には簿記の知識・資格は必要か?
行政書士試験に合格するためには簿記の知識や資格は不要となりますが、行政書士として仕事をしていく上では、簿記の知識は必要となります。
簿記2級レベルの知識を取得しておくと良いでしょう。
なぜ行政書士には簿記2級レベルの知識を要するのか。それは実務において許認可の手続きをする際には、届出書類の一部に財務諸表が含まれることがあるからです。
財務諸表が必要となる場合には、依頼者等から会計経理の内容について質問されることもあります。円滑かつ信頼されるコミュニケーションを十分に図るためにも財務諸表を読む力があると良いのです。
それに、行政書士として独立する方の場合には、確実な事務所経営をするためにも簿記2級レベルの経理知識を持っておくべきだと思います。
経理業務は外注すれば足りると考える人もいますが、自己の行政書士事務所の経営状況を的確に把握するためには会計・簿記の知識は欠かせません。
行政書士と簿記のダブルライセンスのメリットは?
行政書士は書類作成の専門家として、1万種類以上の書類を作成することができますが、簿記と行政書士というダブルライセンスを取得していれば、書類の内容について依頼者からの相談に応じることができます。
行政書士の業務には簿記の力が必要となることが多いので、簿記知識があると他の行政書士と差別化を図ることができる。依頼者からの信頼を勝ち取ることができるでしょう。
簿記は、行政書士の実務において役に立つ資格です。
簿記の検定試験に挑戦する場合には、簿記2級の取得を目指してみましょう。

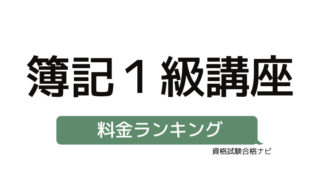
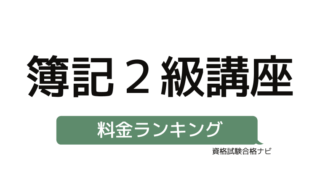
行政書士と簿記検定1級・2級とるならどれ?
今後のキャリアアップに向けて、行政書士試験と簿記1級のどちらを勉強しようか?と考えている方もいることでしょう。
「どちらか一つを選ぶ」
「どちらから勉強するか選ぶ」
選択に迷った場合には、目先では、自分はどちらの資格を取得すべきか?ということを考えてみましょう。
- 経理系の職種で就職したい方であれば「簿記1級」
- 税理士・会計士へのステップアップを視野に入れるなら「簿記1級」
- 法務系の職種に就職したい方であれば「行政書士」
- 独立開業したい方であれば「行政書士」
悩んだ場合には、資格を取得した後に広がる世界を想像してみることが重要です。
資格を取ることで一つづつ人生の選択肢が広がっていくと思います。
湯川七八貴
資格試験受験生のために情報発信を続ける予備校講座の専門家。行政書士試験の合格者からの毎年多くのアンケートを集計し、また各予備校・通信講座の担当者から最新情報を入手するとともに、定期的に情報確認。情報の正確性に注意している
\合格可能性をUP!/
 行政書士には多くの試験対策講座が用意されています。その中には良い講座もあれば、悪い講座もあります。しっかりと見極めて、納得いく講座を選ぶことが重要です。
行政書士には多くの試験対策講座が用意されています。その中には良い講座もあれば、悪い講座もあります。しっかりと見極めて、納得いく講座を選ぶことが重要です。