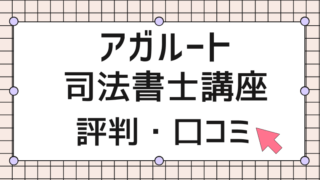司法書士になるための方法をまとめています。
一度確認しておきましょう。
目次
- 1 司法書士になるには?
- 2 司法書士の仕事内容は?
- 3 司法書士試験とは(受験資格・学歴・平均合格年齢〜)
- 4 司法書士試験の難易度
- 5 司法書士試験⇒合格者数・合格率・学歴
- 6 司法書士試験⇒平均受験回数
- 7 司法書士試験の試験科目
- 8 司法書士試験の基準点と受験対策
- 9 司法書士試験⇒合格までの勉強時間
- 10 司法書士試験に合格⇒独学は無理?可能?
- 11 司法書士試験⇒仕事しながら働きながら勉強
- 12 司法書士試験に短期一発合格⇒効率的な学習法
- 13 司法書士試験:予備校・通信講座の評判・比較
- 14 司法書士試験⇒過去問対策
- 15 司法書士試験⇒記述式試験対策・問題集
- 16 司法書士試験の答練
- 17 司法書士試験の直前期対策
司法書士になるには?
(1)司法書士試験に合格すること
司法書士とは、「身近にいる法律専門家」として、全国各地の皆さんに貢献している法律専門職(国家資格)です。
司法書士になるためには『司法書士試験』に合格する必要があります。司法試験のように受験回数の制限などはないので、何度でも受験することが可能です。
ただし、試験を受験しなくても司法書士になれる一定の例外ルートも存在しています。それは、裁判所事務官・裁判所書記官・法務事務官・検察事務官の場合は10年以上の実務経験があることであり、簡易裁判所判事・副検事の場合は5年以上の実務経験があることです。もっとも、実際に司法書士の資格が与えられるためには、口述試験(場合によっては筆記試験も)が実施され、その適性が試されるので、実際のところはハードルは高そうです。
実務家として確実に活躍するために、多くの方は「司法書士試験」に合格する方法で司法書士になっています。
(2)新人研修を受講すること
司法書士試験に合格しても、司法書士になるためには、自分が所属する地域にある司法書士会に登録して、司法書士会が主催する研修に参加しなければなりません。
| ❶中央研修 | (前期日程)12月初旬〜1月中旬の「eラーニング研修」 (後期日程)1月下旬の「集合研修」 |
|---|---|
| ❷ブロック研修 | 各司法書士協議会が、北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の8ブロックに分かれて実施 |
| ❸司法書士会研修 | 各都府県の司法書士会と北海道の4つの司法書士会(札幌・函館・旭川・釧路)が実施 |
上記❶〜❸の新人研修を受講した後に、所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録することで、司法書士として仕事を始めることができます。
(3)認定司法書士になるには
簡易裁判所における訴訟案件の代理業務を行いたい方は、訴訟代理権を持つ認定司法書士になるべく「特別研修」を受講する必要があります。
通常ですと、1月から3月上旬に行われる「特別研修」を受講して、法務省から認定司法書士として認定される必要があります。
司法書士になった後は、司法書士事務所や企業法務部などで働くことができますし、実力をつけた後には独立開業も目指せます。
司法書士の仕事内容は?
| ①不動産登記業務 | 不動産を売買する際に、所有権移転の登記申請をしたり、抵当権設定の登記申請をします。 |
|---|---|
| ②商業登記業務 | 法人の設立する際や、取締役を変更する際に、商業登記申請をします。 |
| ③成年後見業務 | 成年後見の申立書を作成したり、自ら後見人・保佐人・補助人となって高齢者や認知症などの方の財産管理をします。 |
| ④相続・遺言に関する業務 | 相続に際して、不動産の相続登記申請や、家庭裁判所への相続放棄申請をするなど、相続手続きの専門家として貢献します。 |
| ⑤債務整理に関する業務 | 借金返済に際して、個別交渉をしたり、任意整理や自己破産・個人再生の手続きをします。 |
| ⑥簡易裁判所における代理・裁判事務 | 簡易裁判所において取り扱う民事事件(140万円を超えない請求事件)において、当事者の代理人として業務を行います。 |
| ⑦供託業務、筆界特定手続、外国人帰化申請手続 | 供託手続きや不動産の筆界特定手続、外国人の帰化申請手続を行います。 |
司法書士は、法律に関する専門家として、幅広い業務において活躍しています。弁護士や行政書士とも異なり、独自の専門業務を実施しているのです。
司法書士試験とは(受験資格・学歴・平均合格年齢〜)
司法書士試験の基本情報
| 受験資格 | なし |
|---|---|
| 試験日 | (筆記試験)例年7月第1または第2日曜日 (口述試験)例年10月 |
| 筆記合格発表 | 例年9月下旬〜10月上旬 |
| 最終合格発表 | 例年11月頃 |
| 受験手数料 | 8,000円 |
受験資格・学歴
司法書士試験には、学歴や、年齢、性別を問わず受験することが可能です。
社会人経験を経てから受験する方が多いのも特徴的です。
合格者の平均年齢・性別
| 2019年度(平成31年度) | 40.08歳(20歳〜72歳) |
|---|---|
| 2018年度 | 38.77歳 |
| 2017年度 | 37.06歳 |
| 2016年度 | 38.03歳 |
社会人として働きながら受験する方が多い司法書士試験においては、35歳以上の合格者は半分以上です。
30代40代の合格者が7割程で、20代は1割程、50代の合格者は2割弱と言うイメージです。
年齢が何歳になっても、挑戦して活躍できる点に特徴があります。
また、合格者の男女比率でみると、女性合格者は2割以上。5人に1人以上が女性合格者です。
仕事と家庭を両立させることが可能な点で、女性にも人気の資格といえます。
司法書士試験の難易度
後にも述べますが、司法書士試験の難易度は非常に高くて、合格率は3~4%です。国家資格の中でも難関となる試験ですので、合格後の社会的評価は非常に高いと言えます。
弁護士(司法試験)の難易度と比較
司法試験の合格率は、近年では25%で推移することが多いようです。これだけ見ると司法書士試験の方が難関試験と言えそうです。
しかし、司法試験の場合、司法試験の受験資格を獲得するまでに「法科大学院」を卒業したり、「予備試験」に合格する必要がありますし、これらの試験は長期かつ難関試験なのです。
司法書士試験の難易度は、司法試験よりも低いと考えておいて間違いはありません。
司法試験から転向して、司法書士試験を受験する人も多いと思いところ、司法試験に比べて簡単だと油断してはいけません。
気を抜かずに全力で合格を目指す必要があります。
行政書士の難易度と比較
司法書士試験と比較すると、行政書士試験の難易度は易しいと言えます。試験科目数は行政書士の方が少ないですし、合格率(行政書士は10%程度、司法書士は3%程度)も行政書士の方が難易度が低いです。
行政書士試験は、どちらかというと法律初学者が受験しやすい国家試験と言えそうです。
税理士試験の難易度と比較
司法書士試験と比較すると、税理士試験の難易度が若干高いように思えます。
なぜなら、税理士試験は科目合格制度であるものの、5科目の合格率は2%程度なので、司法書士試験の合格率(3〜4%)よりも低いからです。
とは言え、両者とも難易度が高い国家試験であることに変わりはありません。
司法書士試験⇒合格者数・合格率・学歴
司法書士試験の合格者数
| 受験年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 平成28年度 | 16725人 | 660人 | 3.95% |
| 平成29年度 | 15440人 | 629人 | 4.07% |
| 平成30年度 | 14387人 | 621人 | 4.32% |
| 令和元年度 | 13683人 | 601人 | 4.39% |
| 令和2年度 |
司法書士試験は,例年1.5万人程度が受験して,600人弱が合格しています。
近年の資格離れの影響もあり,受験者数は減少傾向にありますが,合格率は概ね3~4%で推移しており,難易度は横ばい状態といえるでしょう。
大学別の合格率
司法書士試験の場合、大学別の合格者数をまとめたデータはない模様です。
しかし、司法書士試験を受験する人は、大学の偏差値で言うと、中程度の大学出身者が多いように感じます。
東大や慶應・早稲田といった大学出身者は、司法試験や会計士試験を目指すことが多いので、司法書士試験を受けることは少ないようです。
また、司法書士試験の場合、大卒の方の他、高卒や中卒の方が合格するケースも多々あります。
過去の合格者を見ていると、必ずしも大卒だから合格しやすいという訳ではないようです。高卒や中卒の方でも、司法書士試験に合格している方を相当数見受けます。
司法書士試験に合格するためには、正しい勉強方法で学習しているのか?と言うことが一番大事だと思われます。
司法書士試験⇒平均受験回数
| 1回で合格 | 10%程度 |
|---|---|
| 2回で合格 | 13%程度 |
| 3回で合格 | 15%程度 |
| 4回で合格 | 12%程度 |
| 5回以上で合格 | 50%程度 |
LEC2018年アンケート参照
司法書士試験は、受験回数が長期化する傾向にあります。
独学で勉強を始めた人に場合には、特に複数回受験をする傾向にあります。
短期合格者から、勉強方法や学習環境について、よく話を聞いて真似をすることが早期合格の秘訣です。
司法書士試験の試験科目
筆記試験(午前の部)
| 試験形式 | 科目 | 問題数 | 配点 | 合計点 |
| 択一式試験 | 憲法 | 3問 | 9点 | 105点 |
| 民法 | 20問 | 60点 | ||
| 刑法 | 3問 | 9点 | ||
| 商法・会社法 | 9問 | 27点 |
筆記試験(午後の部)
| 試験形式 | 科目 | 問題数 | 配点 | 合計点 |
| 択一式試験 | 民事訴訟法 | 5問 | 15点 | 105点 |
| 民事保全法 | 1問 | 3点 | ||
| 民事執行法 | 1問 | 3点 | ||
| 司法書士法 | 1問 | 3点 | ||
| 供託法 | 3問 | 9点 | ||
| 不動産登記法 | 16問 | 48点 | ||
| 商業登記法 | 8問 | 24点 | ||
| 記述式試験 | 不動産登記法 | 1問 | 35点 | 70点 |
| 商業登記法 | 1問 | 35点 |
口述試験
| 試験形式 | 科目 | 所要時間 |
| 口述試験 | 不動産登記法 | 一人15分程度 |
| 商業登記法 | ||
| 司法書士法 |
科目免除
まだ確定的なものではないようですが、新司法書士試験制度が構想されているようです。
新司法書士試験制度のもとでは、法科大学院の卒業者(法務博士)や、予備試験合格者に対して、科目免除の特権を与えるものだそうです。
こちらについては、今後の検討を待ちたいと思います。
司法書士試験の基準点と受験対策
司法書士試験の基準点と合格点
| 受験年度 | 午前・択一(105点) | 午後・択一 (105点) | 記述式 (70点) | 基準点合計 (280点) | 合格点 (280点) |
| 平成28年度 | 75点 | 72点 | 30.5点 | 177.5点 | 200.5点 |
| 平成29年度 | 75点 | 72点 | 34.0点 | 181.0点 | 207.0点 |
| 平成30年度 | 78点 | 72点 | 37.0点 | 187.0点 | 212.5点 |
| 令和元年度 | 75点 | 66点 | 32.5点 | 173.5点 | 197.0点 |
| 令和2年度 |
司法書士試験の受験対策
司法書士試験には、各科目において基準点が設定されているので、基準点を意識して勉強を進める必要があります。
択一式試験の場合、基準点は概ね満点の7割程度に設定されているので、確実に基準点を上回るためにも、合格点を突破するためにも、
満点の8割程度の得点を目指して勉強すると良いでしょう。
簡単な問題はミスすることなく確実に得点するようにしておきましょう。
また、本試験では時間が足りなくなります。午前の択一試験(35問)は120分ありますが,午後の択一試験(35問)と記述式2問は180分で解答しなければなりません。
記述式試験の場合は特に、解答までに時間を要するので、考える時間を確保するようにしましょう。
多くの合格者は、記述式試験に、180分のうちの100分を時間配分しているようです。その場合、午後の択一式試験35問を80分で解く必要があるので,1問あたり2分15秒で解答する必要があるのです。
普段の勉強から、知識を確実なものとするために、反射的に正答を導き出せるように反復継続して問題を解く練習をする必要があります。
主要科目対策
司法書士試験の主要科目は、以下4つです。問題数と配点が多い科目となります。
①民法
②商法(会社法含む)
③不動産登記法
④商業登記法
この4科目だけで、択一式の問題53問(全70問)が出題されます。
司法書士試験に合格するためには、主要科目であるこの4科目から勉強してマスターするようにしましょう。
不動産登記法,商業登記法は,記述式試験でも出題されますし,民法と商法は登記を理解するために前提としてマスターすることが必要な法律なのです。
焦ることなくしっかりと基礎から勉強するようにしましょう。
マイナー科目対策
主要4科目以外の民事訴訟法・民事執行法・民事保全法、供託法、司法書士法、憲法、刑法のことをマイナー科目と言います。
まずは、主要科目から勉強する必要がありますが、マイナー科目の勉強も疎かにしてはいけません。
択一式試験では「合格基準点」があるので、マイナー科目でも合格基準点をクリアしないと記述式の採点が行われないのです。
司法書士試験⇒合格までの勉強時間
目安・最短・平均、1日
| 合格までの勉強時間 | 2000時間〜3000時間 |
|---|---|
| 1日の勉強時間 | 2000時間の場合⇒1日4時間程 |
合格までに要する時間は、合格者それぞれですが、上限3000時間は必要と考えておきましょう。
独学ではなく予備校を利用することが効率学習の観点から重要です。
短期合格者を輩出している予備校や、合格者に評判が良い予備校の講座を受講する必要があります。
社会人受験生の勉強時間
社会人受験生が合格までに必要となる勉強時間も、他の受験生と同じです。
働きながら平日に長時間勉強することは難しいでしょうから、土日や祝日にまとめて勉強する時間を確保する必要があります。
日常の生活リズムの中で、スキマ時間を上手に活用して勉強したり、ストレスなく勉強できるような環境づくりに注意を払いましょう。
働きながら勉強して司法書士試験に合格した方が利用していた勉強法や、予備校を利用するようにしましょう。
司法書士試験に合格⇒独学は無理?可能?
司法書士試験の合格を目指す場合には、特に法律学習経験者は独学を好む傾向があります。
また、費用面を気にして独学で学習する人も多いようです。
しかし、司法書士試験の場合には、不動産登記法と商業登記法という特有の科目があるので、少なくともこれらの科目は独学でマスターすることは難しいでしょう。
特に、合否を分ける記述式試験(不動産登記方・商業登記法)の場合には、合格するためのコツというものがあるのです。
結局、早く合格してしまい、実務家として働くことが費用対効果の観点からも良いのです。
独学で一番怖いところは、偏った勉強をするリスクがあるということです。合格に必要なことに意識を集中して勉強するためには、なるべく独学は避けた方が良いでしょう。
オススメは司法書士試験の予備校を利用することです。
しかし、数ある予備校の中から、質の良い学習ができる予備校を選ぶ必要があります。短期合格者や働きながらの社会人合格者の話をよく聞いて、評判が良い予備校の講座を選ぶようにしましょう。
『どの講座を選ぶか』
これは合否を分ける重要な選択肢となります。
「スキマ時間を有効活用できるか」
「マイペースでストレスが少なく勉強できるか」
「質問や学習サポートがあるか」
「講義や教材の質は良いか」
体験受講をしたりして、納得がいく予備校を選びましょう。
一度講座を選んだら、その講座や教材に集中して、徹底的に繰り返し学習をするようにしましょう。
司法書士試験⇒仕事しながら働きながら勉強
働きながら勉強する方は数多くいらっしゃいます。40代から学習を始める社会人も少なくありません。
平日は仕事で忙しいでしょうが、必ず1日に一回は勉強する癖をつけることが重要です。通勤電車の中だったり、休憩時間だったり、手が空いたらすぐに勉強できるような学習ツールを用意しておきましょう。
オンラインで学習できる予備校教材が役立つと思います。
あと、短時間で良いですから、机に座って落ち着いて勉強する時間を設ける工夫も必要です。
ご家庭がありながら、働きながら合格していく方は相当数います。
他の受験生も頑張っていると思って、モチベーションを維持していきましょう。
司法書士試験に短期一発合格⇒効率的な学習法
主要4科目は,①民法→②不動産登記法→③商法→④商業登記法の順番で勉強しましょう。
マイナー科目は、主要4科目(特に民法)の様子を見て、❶民事訴訟法→❷民事執行法→❸民事保全法→❹供託法の順番で学習しましょう。
その他のマイナー科目(司法書士法,憲法,刑法)は後回しで構いません。
上記科目が落ち着いた段階で、合格に必要な範囲でマスターするようにしてください。
司法書士試験は、出題範囲が広いので全てをマスターすることは不可能だと考えてください。合格するためには満点を取る必要はないのです。
完璧主義は捨て去りましょう。
合格するために必要なことだけに的を絞って勉強することが、合格するためのコツになります。
本試験ではとにかく時間がありません。
瞬時に判断することができるように、骨太の理解と、迷いなく判断できる確実な知識の育成に注力してください。
司法書士試験:予備校・通信講座の評判・比較
司法書士試験:予備校・通信講座の評判
| 資格スクエア | 29万8,000円〜 | 短期合格者と社会人合格者の評判が高いオンライン予備校。 合格にむけた効率学習を実施します。 |
| アガルート | 15万8,000円〜 | 教材に定評がある総合型のオンライン予備校。資格スクエアと迷う受験生が多いです。 |
| スタディング | 10万7000円〜 | 低価格が売りのオンライン型の教材です。機能も充実しており価格重視の方はこちらを選びます。 |
| LEC | 50万円〜 | 従来型の通学型予備校です。自習室が整備されていたり、一部の受験生に人気があります。講座の単発受講をする受験生もいます。 |
| 伊藤塾 | 47万6000円〜 | 従来型の大手予備校で安心感があります。講座料金が高いですが、教材やサポート体制はとても良いです。 |
| ユーキャン | 16万9000円 | 伝統的な通信講座です。ユーキャンが好きな受験生も一定数存在しています。サポート体制は限定的ですが、教材が良いという受験生もいます。 |
司法書士試験⇒過去問対策
過去問対策の勉強法
オススメの過去問講座・教材
司法書士試験⇒記述式試験対策・問題集
記述式試験対策
オススメの問題集・講座
司法書士試験の答練
司法書士試験の直前期対策
\ 無料の体験受講・説明会がある/
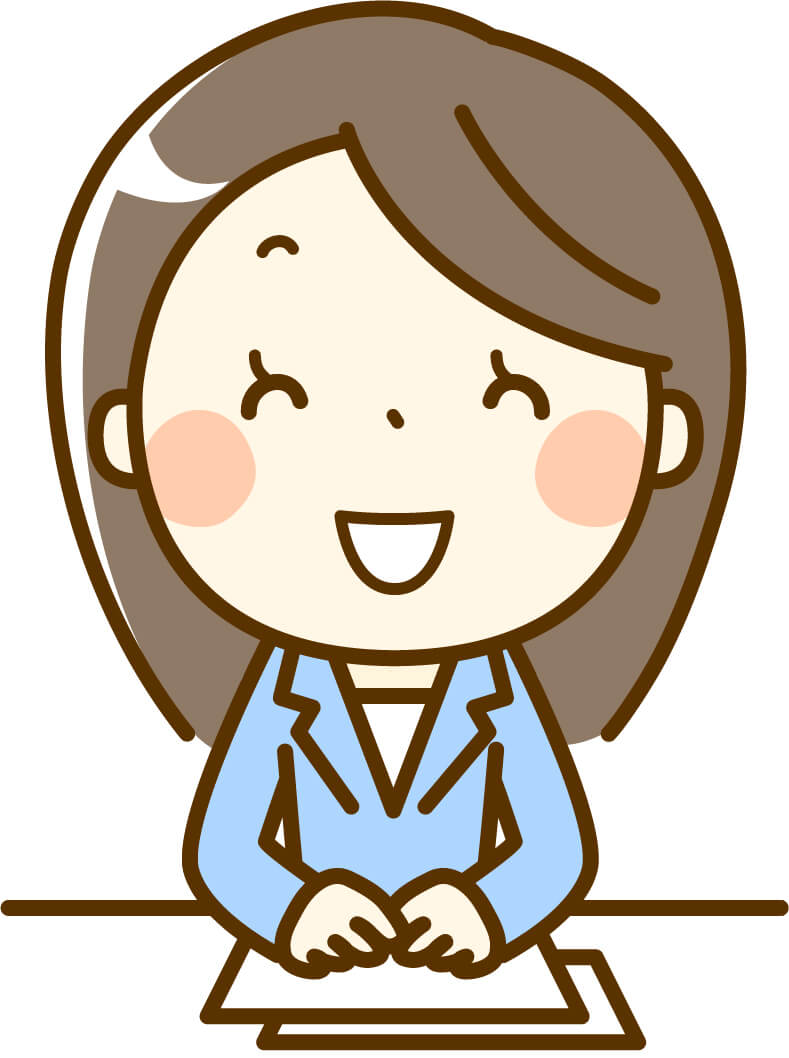 資格スクエアは、合格者にとっても評判が良いオンライン予備校です。
資格スクエアは、合格者にとっても評判が良いオンライン予備校です。
公式HPで必ず確認しておきましょう。