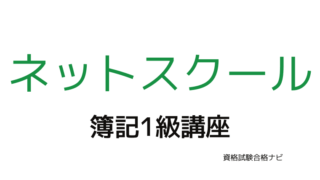- 最短で一発合格するコツ・戦略
- 最短合格のための学習管理
- 過去問の利用法
行政書士試験のオーソドックスな受験生は、受験前年度の9〜12月から勉強始めて、1年間の勉強してから本試験に挑戦することが多いです。
しかし受験生を決意する時期によっては、本試験までの期間が1年を切っていることも多いのが現実。
合格者の中には初学者から勉強を始めて短期間で合格する人も多いですから、受験決意したなら次の試験に向けて今から勉強するべきです。
「3月から勉強して合格」
「半年前の5月から勉強して合格」
「4ヶ月前の7月から勉強して合格」
短期間で合格する方は案外多いもの。
短期集中で勉強した方が、効果的な勉強に意識を集中できるし、無駄な勉強に手を出すこともありません。
正しい最短合格戦略に基づいて勉強すれば、今年度の行政書士試験に合格することは十分可能です。
| 試験日 | 11月第2日曜日 (午後1時〜午後4時まで) |
|---|

目次
最短合格戦略① 合格基準点・足切り制度の理解
最短一発合格に向けて、まずは行政書士試験の制度のポイントを抑えておきましょう。
行政書士試験は「6割180点」を取れば合格する絶対評価方式の試験です。
ただし、注意が必要なのは各科目において足切り点が設定されていることです。厄介なのが一般知識等科目の足切り点で、一般知識等で24点以上取らないといけないこと。この24点を得点できずに不合格となる法律経験者が多いのです。
また、行政書士においては「記述式試験」も出題されるので、この対策も必要となります。
| 択一式(1問4点) | 多肢選択式(1問8点) | 記述式(1問20点 | 配点 | 合計300点満点中 (合格基準は180点〜) | ||
| 法令等科目 | 基礎法学 | 2問 | 8点 | 244点 (足切り:合格基準は122点〜) | ||
| 憲法 | 5問 | 1問 | 28点 | |||
| 民法 | 9問 | 2問 | 76点 | |||
| 行政法 | 19問 | 2問 | 1問 | 112点 | ||
| 商法 | 5問 | 20点 | ||||
| 一般知識等科目 | 政治・経済・社会 | 7(〜8)問 | 28点 | 56点 (足切り:合格基準は24点〜) | ||
| 情報通信・個人情報保護 | (3〜)4問 | 16点 | ||||
| 文章理解 | 3問 | 12点 |
最短合格戦略② 法令等科目対策
行政書士試験において「6割180点」の得点を叩き出すためには、「法令等科目」で得点を稼ぐ必要があります。
「法令等科目」の勉強に学習時間と労力の9割以上を注ぐようにしてください。
とは言っても、試験科目は広範囲に渡ります。とりわけ短期合格を目指す方は満点主義は捨てて、合格基準点を見据えて、合格に必要な学習範囲に的を絞って勉強するようにしてください。
法令等科目における重要科目は「行政法」と「民法」の2科目。この2科目の配点は188点なので、重点的に学習する必要があります。
ここではまず、「行政法」と「民法」が勝負を決める科目だということを頭に入れてください。

最短合格戦略③ 一般知識等科目の足切り点を突破
次に「一般知識等科目」についてです。
一般知識等科目のうち、『政治・経済・社会』の分野は例年いろいろな問題が出題されます。選挙制度や政党について、英米の制度や環境問題についてなど。その他にも文学史や地理の問題、時事問題が出題されることもあります。
どのような問題が出題されるかわからないため、試験対策を立てることが難しい分野なのです。 政治・経済・社会の分野で足切り突破を狙うのではなく、なんとか7〜8問中、2問以上合格できれば、という得点イメージで対策するべきでしょう。
また、「情報通信(IT用語)・個人情報保護」の分野ですが、情報通信とはIT用語について出題されたり、個人情報保護については個人情報保護法について出題されたりします。ここはある程度対策はしやすいので、3〜4問中、2問の得点を狙っていきましょう。
もっとも厄介のが「文章理解」の対策です。
最短合格戦略④ 文章理解対策
一般知識等科目における「文章理解」では、文章の並べ替えや、文章の空欄を補充する問題が出題されます。
文章理解については、そもそも得意な人と不得意な人が分かれます。過去問を解いてみて難なく正解してしまう人は特別対策は不要です。
しかし、苦手意識を持っていたり不得意な人は、文章理解の対策をするようにしてください。
文章理解の問題は簡単な年度では、テクニックだけで解けてしまうこともあります。しかしテクニックを知っているだけでは解けず、使いこなせるレベルまで自分の中に落とし込む練習が必要になります。
学習段階のなるべく早い時期から文章理解対策に着手する必要があります。文章理解の問題は3問中3問正解することを目指してください。
最短合格戦略⑤ 記述式対策
行政書士の記述式試験では、例年、行政法から1問・民法から2問出題されます。
行政法においても民法においても、択一式試験の範囲からの出題となるので、択一のインプット学習をした後に試験対策を始めると学習効果が高くなります。
特に行政法の問題は、択一の過去問から出題されることが多く、定義やら概念についての問題が多いです。
一方民法の問題は、必ずしも過去問から出題されるという訳でもなく、出題方式も年度により色々です。正解するためには要件と効果を暗記しておく必要があります。記述式試験対策は民法の方が難しいという特徴があります。
最短合格戦略⑥ Aランクのみ(勉強範囲の取捨選択)
行政書士試験の出題は、
- 正答率60%以上のAランク問題が、約4割〜5割
- 正答率40%以上60%未満のBランク問題が、約2割〜3割
- 正答率40%未満のCランク問題が、約2割〜3割 です。
ですから、
Aランクの頻出テーマの問題で、皆が正答率60%以上の問題に絞って、徹底的に勉強することです。
これだけのことで、行政書士の合格が見えてきます。
最短・一発合格の効率的勉強法
最短期間で一発合格するためには効率的に学習しなければなりません。
コンパクトにまとまった講義も利用して、知識のインプットから始めます。
全ての試験範囲に全力を傾けるのではなく、行政法と民法・文章理解、については重点的に学習し、その他の範囲は重要ポイントに絞った学習をするようにしましょう。
憲法と基礎法学は重要箇所にポイントを絞り、商法は過去の頻出分野(会社の設立と機関)だけにポイントを絞ることです。
問題演習の際には、過去問を繰り返して演習を繰り返してください。
記述式対策については、独学者も講座を受講するなど、特別の対策を取る必要があります。
最後に模擬試験も受講すると良いですが、時間との兼ね合いで難しい場合には、模試を受講する代わりに過去問演習を徹底して本試験に臨んでも良いでしょう。

最短合格の学習スケジュール管理
ここでは、短期合格のための具体的なスケジュールについて検討します。
便宜的に3月スタートのイメージとしていますが、5月スタートの場合でも、7月スタートの場合でも、同じイメージで勉強してください。
| 法令等科目 | 一般知識等科目 | ||
| インプット | アウトプット | ||
| 3月〜6月 | 民法→行政法→憲法→商法(1回目) | 進捗に合わせて過去問演習を交互に繰り返す | 文章理解から開始 (マスター後に情報通信・個人情報保護) |
| 7月 | 同 (2回目:わからない箇所のみ、倍速で) | 進捗に合わせて過去問演習を交互に繰り返す (間違い問題のみ) | |
| 8月 | 同 (3回目:わからない箇所のみ、倍速で) | 進捗に合わせて過去問演習を交互に繰り返す (間違い問題のみ) | |
| 9月 | 同 (4回目:わからない箇所のみ、倍速で) | 進捗に合わせて過去問演習を交互に繰り返す (間違い問題のみ) | |
3月から学習を始める場合、民法→行政法→憲法→商法の順番で知識のインプットをしてください。
文章理解(一般知識等対策)も、民法と一緒に勉強を始めることが重要です。ただし法令等科目を重点的に学習するようにしましょう。法令等科目にかけるウエイトを95%程度に設定して、同時並行で勉強してください。
また、3月からアウトプット学習も始めてください。知識インプットだけ頑張っても本試験で問題を解けるようになりません。
民法の勉強を始めたら、区切りの良いところで過去問演習を始めてください。最初は読むだけで終わってしまうかもしれません。それでも、インプットとアウトプットを交互に繰り返していくことです。このように知識と演習を繰り返すことで知識が身についていきます。
6月末までに一区切りするようにしましょう。3割程度の完成度で構いません。一番重要なことはとにかく一回しすることに全力を尽くすことです。
7月以降も同じことを繰り返します。インプットとアウトプットを繰り返してください。
講義は2倍速で聞くようにして、外出先や移動時間も利用して、理解不足の箇所に的を絞るようにしてください。
過去問は2周目の問題演習に入ります。2回転目に入り、ここで5割程度の理解率を目指します。
8月以降も同じことを繰り返します。
※5月スタート、7月スタートの人は、繰り返す回数や、1タームの期間を短く設定するなどの工夫をしてください。

行政書士・本試験直前期の学習法
10月になると直前期の期間となります。この直前期に合否が決まると言っても過言ではないでしょう。直前期で勝負が決まります。
直前期に入っても、勉強することは同じです。可能な限り何度も何度もインプットと問題演習を繰り返しながら、間違った問題を中心に全範囲を高速で繰り返してください。
テキストに書き込んだり、間違える問題をあぶり出す作業は、全て直前期のためであります。
何度やっても間違えてしまう問題、理解不足の単元を優先的重点的に学習してください。
直前模擬試験の受講について
直前期に模擬試験を受験することは有効でしょう。過去問演習を何度も繰り返す中で、苦手単元や、よく間違う問題を把握できている人は、本試験の練習として模擬試験を受講すると良いでしょう。
しかし、まだ過去問演習が不十分な方は、時間を有効活用する意味において、模擬試験を受けなくても良いでしょう。
過去問演習を徹底する勉強の方が重要です。
過去問の使い方・勉強の仕方
行政書士試験に合格するためには、過去問演習が必須です。どのように過去問を使って勉強するのかで合否が分かれます。
短期合格を目指すにしても、1年間で合格を目指すにしても、過去問の取り組み方で合否を分けることに違いはありません。
初学者の方が初めて過去問を読んでも内容がわからないはずです。ある程度勉強が進んでから過去問に取り組もうとする人がいますが間違っています。
過去問は学習初期段階から活用しなくては短期合格することは不可能です。
過去問は知識インプット・テキストと相互リンクしながら学んでいくことが重要なのです。 過去問ではどのような知識をどのように問われているのか。だからどのように整理しておけば良いのか。
過去問は知識をマスターしてから解くものではありません。過去問は直関までにどのように知識整理しておけばいいのか?という視点で学んでいくためのツールとして利用することです。

独学でも行政書士試験に合格可能か?
市販のテキストを使って独学で行政書士試験に合格することは、確かに不可能ではありません。
しかし、初学者の場合は特に独学はオススメできません。学習経験者の方でも文章理解が苦手な方はやはり独学での合格は難しいと思います。
合格するための勉強方法論が確率しており、コンパクトにインプット学習ができる講座をえらで勉強することが重要だと思います。特に短期合格するためには良い講座を受講することが必須だと思います。
オススメの行政書士試験対策講座は?
合格に的を絞り込んだコンパクトな教材を使い、合格者や予備校講師が推奨するカリキュラムに従い、勉強することが大事です。
合格者やプロの先生のアドバイスに素直に従うこと。その教材を信頼して勉強できることが重要です。
料金が高い講座が良い講座ではありません。行政書士試験の場合、幸いなことに最短合格を目指せる良質な教材は、低価格のものが多いです。
合格者に評判が良い講座は下記3つです。
- アガルート(オンライン講座)
- フォーサイト(通信講座)
- スタディング(最低料金の講座)
以下のページでも短期一発合格を狙える講座についてまとめているので、読んでみてください。

湯川七八貴
資格試験受験生のために情報発信を続ける予備校講座の専門家。行政書士試験の合格者からの毎年多くのアンケートを集計し、また各予備校・通信講座の担当者から最新情報を入手するとともに、定期的に情報確認。情報の正確性に注意している
\合格可能性をUP!/
 行政書士には多くの試験対策講座が用意されています。その中には良い講座もあれば、悪い講座もあります。しっかりと見極めて、納得いく講座を選ぶことが重要です。
行政書士には多くの試験対策講座が用意されています。その中には良い講座もあれば、悪い講座もあります。しっかりと見極めて、納得いく講座を選ぶことが重要です。